
塾長・最高顧問 元谷 外志雄
勝兵塾第41回月例会が、10月16日(木)、アパホテル〈東京潮見駅前〉にて開催されました。
アパグループ代表元谷外志雄塾長による開会のご挨拶では、「昨日第7回懸賞論文の審査会が行われたが、その中でこの6年間の世の中の変わり様を実感した。6年前は朝日が『アパを潰す』と言い、表彰式を止めさせようとしたが、今はアパが『広告を止める』と言って朝日を追い込んでいる。今回の最優秀賞には次世代の党の衆議院議員杉田水脈氏の『慰安婦問題とその根底にある報道の異常性』が選ばれた。この論文にはプレスコードの30項目が載せられており、これを英訳して発信する意義は大きい。優秀賞社会人部門は国際大学グローコム客員教授青柳武彦氏の『日本の最大の敵は日本人の自虐史観だ』が、同学生部門は筑波大学大学院2年日置沙耶香氏の『特攻・回天~真実の日本の歴史を発信する秋が来た~』である。今回は14歳から92歳まで幅広い年齢層の応募があり、入賞者の最高齢が88歳で、この方は元日本海軍艦上爆撃機のパイロットである。入賞者の中には勝兵塾で講師をしていただいた方も多くおられ、勝兵塾と懸賞論文、さらにはアップルタウンのエッセイやBig Talk、ワインの会の記事が世の中の保守化傾向に貢献している。日本の政治家の多くは立ち位置がしっかりしていない。しっかりしているのは次世代の党と太陽の党くらいである。安倍自民政権が極右と見られることにならない様にするために、その右に次世代の党、さらにその右に太陽の党が来れば、安倍政権は中道政権になる。次の選挙では太陽の党に頑張ってもらい、次世代の党と共に安倍自民党と連立を組んでほしい。公明党はアメリカの利益を代弁し、尻尾が胴体を振り回しているのが現状である。次の選挙では保保連立政権となることを期待している。世の中全体が本当のことを理解すれば、世の中は変わる。朝日が誤報を認めて謝罪したが、追撃の手を緩めてはいけない。杉田議員の論文の最優秀賞受賞は、アメリカが言論の自由を封じていたことをアメリカ自身に知らしめる良い機会となる。」と、第7回懸賞論文の審査結果を披露されるとともに、将来の保保連立政権誕生への期待を述べられました。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄様
太陽の党代表幹事・国民運動本部長で第29代航空幕僚長の田母神俊雄様は、「9月25日に太陽の党を立ち上げ、西村眞悟氏を代表とした。6月の初めに新党をつくると宣言したが、政党をつくるためには現職国会議員が5名必要であり、時間がかかると思っていたところ、石原、平沼両氏から、『太陽の党が現在休眠しているから、これを使えば』と、お話をいただいた。新党設立宣言をしたときは大変厳しい批判もあったが、宣言しなければこんな話はなかった。安倍政権の日本を取り戻す政治を応援していきたい。次世代の党が自民党の右にしっかりとした柱を立てて自民党を支え、太陽の党は次世代の党がやりやすいように砕氷船の役割を果たす。戦後アメリカによって戦前の日本が壊された。経済力を取り戻すのも大切だが、戦前の日本を取り戻すことがより大切である。戦前の日本は、人類の歴史上ないくらい安心して暮らせる国だった。家督相続制や大家族制度が壊され、東京都では一人暮らしの老人が70万人もいる。昔は親の面倒は必ず子が見るものだったが、家督制度が壊されたために孤独死が増えた。さらに介護や子育ての問題もある。核家族化によって親が子を虐待し、子が親を殺すようになった。大家族制ならこんな問題は起こらないだろう。税の誘導によって変えていくべきである。」「日本を普通の国にしていかなければならない。日本だけは兵器の開発を秘密でできず、世界に公言してからやっている。日本では国を守ることが言えない。核兵器は二度と使われることはないが、持っているかどうかで発言力が違う。核武装の話をしておかしいと言うのはアメリカ派である。軍事力が強い方が、国が安全なのは当たり前で、国際政治の常識と全く違うことが日本では言われている。これからタブーに切り込んでいく。次世代の党が言いにくいことは太陽の党が言っていく。」と、太陽の党としてこれから目指す政治活動への抱負を語られました。た。

関西学院大学国際学部教授 鷲尾友春様
関西学院大学国際学部教授の鷲尾友春様は、「JETROで対外情報発信をしてきた。対外PRにおいて、相手が聞きたいと思う瞬間にボールを投げ込むことが重要である。1994年2月には、当時の細川首相がクリントン大統領と会談して、Noと言って帰ってきたが、そのとき私はNYタイムズに、『アメリカが勝手にイメージを作って、そのイメージと現実が違うと日本のせいにする』といった内容の記事を寄稿した。日越国交35周年を記念してベトナムから訪日団が来日した際には、現地の新聞に、『日本はベトナムに、蒙古襲来と日露戦争で過去2度助けられた。』といった内容の記事を寄稿した。10月に学生を連れて東南アジアを訪れ、定点観測している。昨年、東京オリンピックが決まったときに現地の英字新聞を買い集めたが、東京の勝因として、ソチやブラジルで準備が遅れていたため、オリンピック委員会もこれ以上準備が遅れるのは困るから、『日本なら大丈夫だろう』という信頼感があったと一様に書かれていた。日本は、新幹線を2、3分おきに走らせることができ、ごみの収集をシステマティックにやっているユニークな国だ。国際社会においても、日本的価値観を前面に出しながら、長期戦を粘り強く戦っていく必要がある。」と、対外的な情報発信について語られました。

拓殖大学客員教授 藤岡信勝様
拓殖大学客員教授の藤岡信勝様は、「今年一年で最も嬉しかったことは8月5日に朝日新聞が落城したことである。吉田清治の証言を虚偽と断定し、16本の記事を取り消した。私は教科書問題に取り組んできたが、朝日は天敵だった。慰安婦強制連行はこれで完全に挫折したが、朝日は朝鮮人強制連行と南京大虐殺についても嘘を認めてから廃刊してほしい。『朝鮮人強制連行』は1960年に作られた話で、当時朝鮮総連が北への帰国事業を日本政府が支援すべきと主張したことの根拠として、『朝鮮人が好き好んで来たわけではない』と発言しことが『強制連行』という言葉に変わり、奴隷狩りをイメージさせるようになった。実際には朝鮮人はより良い生活を求めて日本に来たのだが、これに対して日本人が全く反論しなかったために、ついには教科書に載るようになった。『従軍慰安婦』という言葉は千田夏光による造語であり、『性奴隷』という言葉は弁護士の戸塚悦朗の妄想である。戸塚氏が思いつきで国連人権委員会に持ち込んだら大きな反応があった。糾弾のためのキーワードを作り、連想されるイメージに合った話を作り、最後に証人が現れる。朝鮮人慰安婦の強制連行が無かったと断定できる根拠は4つある。強制連行に関する指令書が皆無であること、執行した側の人物の証言が皆無であること、目撃者の証言が皆無であること、強制連行の被害を破綻なく証言した人物は皆無であること、である。無かったことの証明は論理学的には不可能だが、社会生活上は根拠が無いことで十分である。『悪口を言った者勝ち』の社会を許してはならない。慰安婦の強制連行は学問的には1992年に決着していたが、論点をすり替えながら拡散され、河野談話が出てからは談話そのものが証拠となった。日本政府が誤った対応をしてきたからグレンデール市をはじめ慰安婦像が設置されるようになった。慰安婦像撤去訴訟が提起され、在米日本人が初めて声を上げた。」と、慰安婦問題の論点や経緯を解説されました。

ラ・ロシェル店主 坂井宏行様
ラ・ロシェル店主の坂井宏行様は、「今、日本の料理界は世界から注目されている。昨年、和食が世界文化遺産に登録された。つくる料理人のレベルを上げ、次の世代につなげていく必要がある。美味しいものと不味いものの両方を食べないと美味しいものが分からない。美味しいものだけを食べても幸せにはなれない。料理は人間の胃袋を満たすだけでなく、会話や雰囲気を楽しむためにも大事なものである。先日佐世保の海上自衛隊に招かれ、海軍カレーを監修してほしいと頼まれた。イージス艦の乗員300人に対して料理人は7人しかいない。厳しい環境の中で料理をつくっている。私も海軍カレーを食べて見たが美味しかった。食欲は人間の三欲の一つであり、無くては生きていけない。フランス料理は儲からない。しかし夢、ロマンがある。『料理の鉄人』という番組の貢献は、料理人のレベルを上げたことである。6年半に亘り鉄人としてやったが、ルールが厳しかった。調理時間は1時間しかなく、テーマがわかるのは本番2分前で、その中で4皿6人前を作らなければならなかった。厳しい環境の中でとても素敵な時間を過ごした。」と、料理に対する思いを語られました。
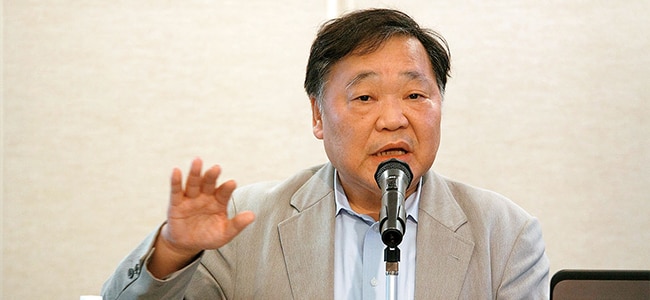
国際教養大学教授・図書館長 勝又美智雄様
国際教養大学教授・図書館長の勝又美智雄様は、「Vision(理念)、Mission(使命)、Passion(情熱)を持ってこの10年間、国際教養大学(AIU)を育ててきた。AIUは2004年に開校し、1年で、東北地方で東北大学に次ぐ難関校となり、2年で、関東以北で最難関校となった。全ての授業を英語で行い、1年間の留学を義務付けている。そのため世界中で165校と提携している。教職員をプロに育てている。提携校を増やすためには外国の大学のカリキュラムやシステムを良く知っている人材が必要である。公務員は3年で異動してしまうので、国立大学、県立大学では絶対にできない。さらに1年間で430の高校を回り、マーケティングをしっかりやっている。全校生徒は870人で、全国から学生が集まっている。96名の教職員のうち6割は外国人であるが、授業を全て英語で教えるから日本語は話せなくても良いと考えている。図書館は24時間365日オープンしている。こうした大学ができたのは当時の寺田知事の執念と中嶋嶺雄理事長の情熱があったからだ。」と、短期間で大きな成果を収めている国際教養大学の理念と取り組みについて語られました。

日本理事長 白石ユリ子様
NPO海のくに・日本理事長の白石ユリ子様は、「日本は世界で6番目に広い海を持つ海洋国家である。世界はこれまで肉を食べてきたが、今世界は魚を食べ出した。一方日本では魚と肉の消費量が逆転してしまっている。しかも日本で消費される魚のうち、日本の魚は5割しかなく、世界147カ国から2兆円も輸入している。この矛盾を誰も知らないことが問題である。漁村や漁業の現状を子供達に伝えていかなければならないと考え、『ウーマンズフォーラム魚』を立ち上げた。東京の小学校に浜のお母さんを講師として招き、魚料理を作ったり浜の現状について話をしていただいたりしている。さらに小学生を対象に、漁村でホームステイをして漁師体験を行ったり、漁村を取材した子供達がその体験を子供フォーラムというかたちで発表したりしている。また、日本にこれだけ広い海があるのは離島があるからであり、日本の国のかたちを学ぶため離島の授業も行っている。海上保安庁を訪れたり、実際に小学生を離島に派遣し、取材させて、取材成果を発表させている。全国の小学校で鯨の授業を進めるとともに、NGOとしてIWCに出席し、ロビー活動を行っている。こうして海と魚を通して子供達に日本の姿を伝えている。」と、海と魚を通じて日本を知る運動の取り組みについて語られました。

自民党広報本部長 馳浩様
衆議院議員で自民党広報本部長の馳浩様から、肉と魚の子供の成長への影響について質問が出され、白石様は、「日本人は元々魚食民族であり、そのように体ができている。歴史上日本人ほど急激に食生活が変わった民族はない。さらに現在世界中が和食に注目している。魚はヘルシーであり、体に優しいので、子供達には魚を食べさせてほしい。」と答えられました。さらに藤岡様より、「資源に限りがあるのであまり和食を宣伝すべきではないのではないか。」という意見が出され、白石様は、「本来、一汁三菜と言われるように、和食の大半は野菜であり、魚はごく一部である。中国の山奥に回転寿司を広めた会社があり、日本は世界中で中国に魚を買い負けている。だからこそ、昔からある和食に戻るべきである。」と答えられました。

セントルイス大学教授 サー中松義郎博士
セントルイス大学教授のサー中松義郎博士からは、「国連で日本は常任理事国になりたいとお金をつぎ込んでも、敗戦国である以上、絶対になれない。別の国際組織を創って日本がその中心になるくらいの大きな構想が必要だ。」という意見が出されました。また、新しい歴史教科書をつくる会副会長の岡野俊昭様は、3週間にわたってコロンビアを訪問されたことに触れられ、「現地の日系人は、『日本人の心を忘れるな。』という気持ちを持っている。」と、日系人の思いを語られ、勝兵塾事務局長の諸橋茂一様からも、ブラジル日本会議の徳力理事長の、「ブラジルにいる私達は、日本にいる日本人と違い、素直な気持ちで戦前の素晴らしい日本を受け継いでいる。なぜ今の日本人は日本に誇りを持てないのか。」という言葉が紹介されました。
最後に塾長より、「10月3日の産経新聞に、原田義昭氏が委員長を務める自民党国際情報検討委員会が朝日新聞の慰安婦問題に関する過去の報道に対して、『虚偽の記事が国際的な情報メディアの根拠となり、国際社会がわが国歴史の認識を歪曲し、国益を著しく毀損した』と非難する決議を採択したという記事が掲載された。日本の名誉回復に向けて国連をはじめ全ての外交の場、官民挙げての国際交流の中で、正しい主張を訴え続けることや諸外国の動きを鋭敏に察知し、国の対応を機敏に行うことが必要だとして、政府の積極的な対応を求めている。自民党の中の委員会がこうした決議をしているのだから、政府は河野談話を撤回し、朝日が少し謝罪しただけでお茶を濁し、逃げ切らせてはいけない。自民党は決議したことを実行してほしい。」と、勝兵塾講師特待生でもある原田様が中心となった自民党内の活動を紹介され、会を締め括られました。
研修会の後は、レストラン「ラ・ベランダ」に会場を移して懇親会が行われ、研修会での流れのまま活発な議論が尽きず、予定時間を大幅に超過する盛況ぶりでした。


