
塾長・最高顧問 元谷 外志雄
第54回勝兵塾月例会が、11月19日(木)にアパグループ東京本社会議室で開催されました。
冒頭のアパグループ代表元谷外志雄塾長による開会のご挨拶では、「先日ニューヨークへ行った。パートナーと現地法人を作り、そのパートナーが保有する、ニューアーク空港から車で20分、電車で2駅30分のところにあり、今までヒルトンブランドで運営されたホテルをリブランドして、11月13日にアパホテルとしてオープンした。その前日にはマンハッタンで記者会見を行ったので、その模様を見ていただきたい。」とアパホテルのアメリカ進出について披露され、記者会見と第一号ホテルの開業式典の模様を動画で視聴しました。

新しい歴史教科書をつくる会副会長 藤岡信勝様
新しい歴史教科書をつくる会副会長の藤岡信勝様は、「南京大虐殺がユネスコ記憶遺産に登録されたことのどこに問題があるのか話したい。本当は登録を阻止することは可能であったが、外務省が力を尽くさず、国民に明らかにされなかったために阻止できなかった。11月12日にBSフジのプライムニュースという2時間の生放送に出演した。私は、南京大虐殺はなかったという立場で出演したが、他に十数万人説の山田朗氏と4万人説の秦郁彦氏が出演した。私はこの番組に出演していろんなことがわかったが、その中でも驚いたことは、秦氏がその後の研究成果をほとんど咀嚼していなかったことだ。秦氏が中公新書の『南京事件』という書籍を書いた頃は、マンチェスター・ガーディアンのティンパーリは中立なジャーナリストだと言われていた。しかしその後の調査で、彼は中国国民党の中央宣伝部の顧問であり、金をもらって国民党のエージェントとして振舞っていたことがわかった。曾虚白は自伝の中で『国際宣伝は中国人が自ら前面に出るのではなく国際友人を探して代弁してもらうべき』と書いている。当時中国にいる宣教師は例外なく国民党の宣伝に関わっていた。秦氏は新書の中で、ティンパーリやベイツの言っていることを、全く疑いを持たずに根拠としている。秦氏は慰安婦問題では吉田証言の嘘を暴き、その功績は大きいが、南京事件では本多勝一に次いで負の影響を及ぼしている。秦氏の本の影響は大きく、しかも未だに当時と知識は全く変わっておらず、日本軍を糾弾するのが正義だと信じていた。戦時国際法では自己保存の原則というものがあり、当時2、000人の日本兵が自分達の身を守る必要があったが、不必要な大量殺戮はしていない。この点は日本人についてどう見るかという解釈の問題でもある。」と、南京事件のユネスコ登録に関する問題点を指摘されました。

史実を世界に発信する会事務局長 茂木弘道様
史実を世界に発信する会事務局長の茂木弘道様は、「自民党の国際情報検討委員会でユネスコ問題について討議したが、結局のところ、政治家や文科省や外務省の官僚が、虐殺があったと思っているところにある。平沢先生は『虐殺の数はいろいろ説があるが虐殺が合ったことは日本政府も認めている』と発言していた。政府見解の根拠は何かと言えば、歴史学会の定説である。文科省も外務省も学会の説をベースとしている。北岡伸一氏は『南京事件を否定する学者は一人も居ない』と堂々と言っていたが、確かに歴史学会に南京事件を否定する者はほとんどいない。しかし、これを変えていかなければならないのだ。また、多くの人が、程度はともかく日本が中国を侵略したのは疑いようがないと思っており、『歴史認識』と言われた途端におとなしく頭を下げてしまう。贖罪意識を持つことが良心的であり高尚であると思っている知識人、学者が多い。私は世界に向けて英語で南京事件を否定する根拠を発信したが、オランダの学者が『学問的にも道徳的にも程度が低い』と言ってきた。胡錦濤が来日した際、南京事件について公開質問状を出した。これに答えられなければ南京事件は嘘だと言えるが、もちろんこれまで答えていない。満州事変で日本軍はたった1万4百の兵力で25万の張学良軍を駆逐し、日本の2、3倍もの広大な満州を2ヶ月足らずで占領した。こうしたことができたのは民衆の圧倒的な支持があったからである。日本統治時代の満州の経済成長はすごく、アメリカの経済学者シュムペーターの奥さんが本に書いたくらいである。これが侵略と言えるだろうか? 盧溝橋事件については、共産党が起こした事件であることが今では明らかになっている。上海事変は実際には戦争であったが、中国による侵略であった。これは反日のニューヨークタイムズでさえ、『日本軍は中国軍によって文字通り衝突へと無理やり追い込まれていった』と書いている。日本人にとって幸せなのは、本当のことを言えば絶対に勝てることである。」と、南京事件を中心に、日本が中国を侵略したのではないことの根拠を示されました。

慶應義塾大学経済学部教授 塩澤修平様
慶應義塾大学経済学部教授の塩澤修平様より、「公開質問状とはどんな内容か」と質問があり、茂木様は、「①毛沢東は生涯ただの一度も南京大虐殺について触れていないがなぜか? ②国民党中央宣伝部は漢口で外国人記者を招いて会見を300回開いているが、ただの一度も南京大虐殺について触れていないがなぜか? ③国際委員会の『Documents of Nanking Safety Zone』の中で南京の人口は日本軍による占領直前の12月に20万人、1ヶ月後の1月に25万人となっているがどう考えるか? ④同文書に殺人事件の記録が26件、うち目撃があったものは1件であり、その1件は不法殺害ではないと書かれているが、どう考えるか? ⑤南京事件の証拠とされる写真はこれまで東中野先生らの研究で南京大虐殺を示すものは1件もなかったことが明らかになっているが、南京で虐殺があったことを示す写真があれば提示してほしい、という5点である。」と、公開質問状の内容を解説されました。
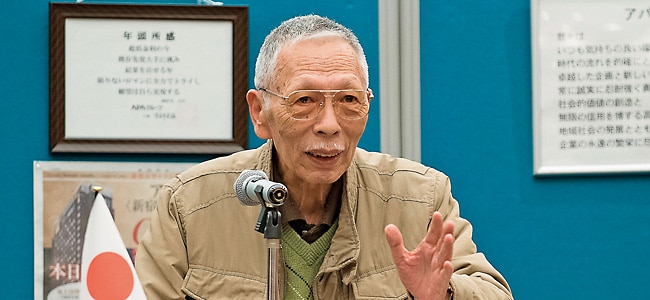
元「国際放映」プロデューサー 小林繁之様
元「国際放映」プロデューサーの小林繁之様は、「バリに住んで12年になる。元々テレビのプロデューサーとしてバリでネタを探していたら、『バリ島の父』と呼ばれる方のことを知り、その功績を調べ始めたら深く広く、未だに続いている。バリ島は世界有数の観光地であり、バリ島に行くと多くの日本人はマリンスポーツを楽しむ。しかし、バリ人から見ればなぜそうなのかと思う。インドネシアが独立できたのは日本軍のお陰である。日本人がインドネシアを侵略し、占領したと言われるが、その当時はインドネシアというものはなく、350年に亘るオランダの植民地支配が続いていた。教育の機会は王族の子弟にしか与えられず、オランダに従順なように国民に教育を与えなかった。それが日本軍はわずか3年半の間で大きく変えた。バカを育てるシステムから、オランダに対して独立を挑むだけの知力、体力などの能力を身に付けさせたのだ。だからインドネシア人、特にバリ人は日本人に対して感謝の念を今でも強く持っているのである。バリ人が日本人に対して大変親切なのは、こうした話を祖父や父から聞いているからだ。日本の終戦後、インドネシアの独立戦争でバリ人に協力し、バリ人のために死んでいった旧日本兵たちはバリ島の父、バリ島の神として語り継がれている。『バリ島の父』と呼ばれた三浦襄の墓は未だに大切に管理されている。また、マルナガラの英雄墓地には11名の日本人が祀られており、墓碑の頭には赤と白のリボンが巻かれている。慰霊祭にはそこを訪れた人々が必ず花を手向けている。こうしたことがなぜ日本の書物に出ないのかと思う。」と、バリ島でインドネシアの独立のために活躍した日本人について語られました。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄様
第29代航空幕僚長の田母神俊雄様は、「米中軍事超大国と言われるが、実際は全く嘘である。アメリカはリーマンショック後に軍事費を10年間で50兆円削ることになっているが、これでは軍需産業が困るため、『中国が強いのに軍事費を削っても良いのか』とアメリカの政治家や国民に対して情報戦を行っているのだ。さらに、日本に対しても同様に『もっと金を出せ』と情報戦を行っている。しかし中国が軍事超大国であるというのは虚構である。防衛省をはじめ、各省庁は白書を出しているが、嘘は絶対書かないが、出す情報は自分達の仕事がやりやすくなるように選んでいる。防衛白書によれば中国の陸上兵力はすごいように見えるが、日本には歩いて来られないのでその数に意味はない。海上兵力はアメリカの624万トンに対して中国は147万トンであるが、隻数ではアメリカは949隻であるのに対して中国は871隻と余り変わらない。つまり中国の船は小さく半数以上は海洋作戦に使えないのである。航空兵力では中国が2、600機であるのに対して、日本は410機となっているが、中国の戦闘機で使えるのは400機くらいだろう。さらに戦闘機は稼働率を維持するのが難しく、自衛隊は稼働率が80%であるのに対して、中国は50%くらいだろう。また、戦闘機が飛ぶためには金がかかり、1時間あたり200万円くらいかかる。そのうち80%が部品代である。そのため、中国軍のパイロットの年間飛行時間はサンデーゴルファーみたいなものである。中国は、後10年間は尖閣を占領する軍事力は持てないだろう。しかし中国に脅されている政治家が多い。中国は安倍総理が自衛隊を使うことを最も恐れているため、情報戦をしている。戦争をするためには少なくとも半年の準備が必要である。しかし中国は戦争の準備をしていない。領海に入ってきた船は沈めればよい。情報戦にやられて『尖閣くらいを手放してもよい』とならないことを願っている。」と、中国の戦力の実態を明らかにされ、情報戦に負けないう警鐘を鳴らされました。

元帝京大学教授で新社会設計研究所所長 宮崎貞行様
元帝京大学教授で新社会設計研究所所長の宮崎貞行様は、「鬩ぎ合う日米中の国体神話について話したい。どの国にも国体神話があり、現在は神話戦争の時代に入ってきたと言える。日本社会は行き詰っており、このままで良いのかと国民が感じている。戦後日本の建国神話はアメリカからの借り物の『自由』と『民主主義』である。これらはジェファーソンが独立宣言の中で表明しているが、アメリカでは先住民インディアンの自由と独立は認めなかった。あくまで白人の自由である。つまり自由の背後には弱い者を利用する覇権主義がある。アメリカでは貧富の格差を助長し、社会の対立を強調している。自由を協調すればするほど対立を生み、弁護士を大量に生み出す訴訟社会となる。欲望をむき出しにした強欲である。中国共産党は当初は『全体の平等』を掲げていたが、共産主義は活力を削ぐことが分かり、『原始資本主義』に戻っている。それはアメリカを上回る貧富の格差と腐敗を生み出し、現在は弱肉強食の中華思想が国体神話となっている。『力は正義なり』として、チベットや新疆ウイグルを弾圧し、南シナ海などで資源を強奪し、嘘も百回繰り返せば真実になるとしている。戦争の背景には神話の対立が隠れている。我国はのんびり傍観している場合ではなく、独自の国体神話を発信すべきである。日本の国体神話の原型は古事記にある。古事記には三種の神器として表現され、歴代の天皇と臣下が受け継ぐべき建国の理念を示している。これが聖徳太子の十七条憲法で『和の理念』となり、二宮尊徳の『報国思想』として体系化され、共同体の発展のために奉仕し、助け合い、譲り合う精神となった。現在の日本はアメリカの思想的植民地になっているが、東日本大震災ではまだ日本にこの精神が残っていることが証明された。日本の『和の精神』を精緻な形で言語化し、世界に向けて発信し、指導していって欲しい。」と、日米中の国体神話について概説され、日本の「和の精神」を発信していくことの必要性を訴えられました。

勝兵塾事務局長 諸橋茂一様
勝兵塾事務局長の諸橋茂一様は、「先日、ニューヨークへの海外研修に参加し、自由行動の日にポーツマスを訪れた。日露戦争時の日本とロシアの戦力比はおよそ1対10であった。当時のロシアは世界一の陸軍大国であり、日本政府もよくわかっていたので、戦闘を短期間で決着させ、優位な時点で講和に持ち込む必要があると考えていた。そこでハーバード大学留学中にセオドア・ルーズベルトと同窓であった金子堅太郎をアメリカに派遣した。1905年3月10日に奉天で日本が大勝、5月27日から28日には日本海海戦で世界の海戦史上類を見ない完勝を収めた。なお、東郷元帥は世界の三代提督と呼ばれているが、その中でも最も尊敬されている。講和に持ち込むのに良い時期だと考えた日本政府は、小村寿太郎を米国に派遣し、ルーズベルト大統領に調整を依頼した。当時ルーズベルトは新渡戸稲造の『武士道』を読んで感動し、日本に対して好感を持っていた。そこで講和の会場としてポーツマスが選ばれた。8月1日から17回に亘って会談を行い、現地時間の9月4日にポーツマス条約が結ばれた。ニコライ二世はウィッテに対して、賠償金、領土は一切渡すなというスタンスで臨むよう指示していた。日本では勝ったという報道が続いていたため、多くの国民は賠償金や領土が取れるだろうと期待していた。小村寿太郎は一歩も引かず頑張り、北緯50度以南の樺太や南満州鉄道の権利など相当多くの譲歩を引き出したが、政府もマスコミも会談の困難さを国民に伝えず、賠償金を取れなかったことで国民は怒り、日比谷焼き討ち事件が起こった。」と、ポーツマスでの日露間の厳しい交渉について語られました。
最後に塾長は、「7年前に田母神氏が第一回の懸賞論文で最優秀賞に選ばれたことで大騒動が起こったが、これが大きな覚醒効果となって安倍総理の再登板にも繋がったと言えるだろう。第八回はケント・ギルバート氏が選ばれ、12月8日のパーティーでは講演していただくことになっているので、できるだけ参加していただきたい。毎回論文集を出版しているが、あわせて今年は個人的なことを含めた新しい本を書いている。間に合うか微妙なところであるが、タイトルは『逆境こそ光輝ある機会なり』で、私が中学の卒業アルバムに書いた言葉である。なお、小学校の卒業アルバムでは将来なりたいものとして『世界連邦大統領』と書いた。事業を起こすために金融を学ぼうと信用金庫に入社するとともに、慶應義塾大学経済学部通信教育部に入学した。すると松井秀樹選手のお父さんが隣町に住んでいたのだが、たまたま同じ年に同じ通信教育部に入学した同窓だった。厳しいときにどう乗り切っていくかが大切であり、自由闊達に奔放に生きてこられたことが、今日の成功に繋がっている。本のサブタイトルは『今から始まるアパの世界戦略』である。パーティーに参加された方にはお土産として配る予定だ。また、今月の座右の銘は『人生は短い 未来と闘う過程を楽しみ 時間に負けるな』である。」と、懸賞論文集の出版記念パーティーへの参加を呼びかけられるとともに、執筆中の書籍について紹介されて会を締め括られました。


