
塾長・最高顧問 元谷 外志雄
勝兵塾第40回月例会が、9月18日(木)、アパホテル東京潮見駅前にて開催されました。
アパグループ代表元谷外志雄塾長による開会のご挨拶では、「本日の夕刊フジの1面にテキサス親父ことトニー・マラーノ氏との対談記事が出ている。8月16日付の夕刊フジに掲載されたインタビューの『朝日への広告やめる』という記事から、朝日に対して様々な批判が出てきた。先般朝日は謝罪会見をしたが、国家に与えた損失は天文学的であり、そんなものじゃ済まされない。これまで朝日は日本の言論界を牛耳ってきた。朝日を批判できるメディアはないという傲慢さがあり、誰もがおかしいと思いながらも朝日に従ってきた。プレスコードを逸脱するものは徹底的に叩くということで、6年前の12月1日の朝日新聞には1面の題字のすぐ横に『アパ代表選考主導』と大きく掲載された。懸賞論文の審査で私が意図的に田母神氏を選んだということだが、審査員によって選ばれた3名の優秀者のうち誰が良いかについて私は意見を言ったが、私が懸賞論文の主催者であり、何がおかしいというのか。当時は会社にも自宅にも報道陣が殺到し、警察からは殺害予告が出ているから警護するという申し出まであった。懸賞論文の表彰パーティーは当初、外国大使や国会議員等、数多くの方々を発起人とする予定であったが、発起人名簿に記載された方々に朝日から執拗な攻撃があり、辞退者が相次ぎ、発起人形式を止めて私の主催とした。田母神論文が最優秀賞に選ばれたことが相当の脅威だったのだろう。左傾化していた麻生自民党末期政権が選挙で敗れて誕生した民主党政権はさらに酷かったため、自民党が再び大勝した。」「先日次世代の党の結党大会が盛大に行われたが、これをどう報ずるのか翌日の新聞に注目した。産経、読売、朝日、日経の四紙を比べて読んで見た。多くの人々は産経に次ぐ保守は読売だと思っているが、最も小さいベタ記事の扱いだったのが読売で、朝日より小さかった。読売は左傾化している。朝日の社長は退任に追い込まれると思うが、次に注目すべきは読売新聞だろう。」と、言論界を牛耳ってきた朝日の傲慢さへの批判に留まらず、読売の左傾化についても指摘されました。
8月26日(火)に開催された勝兵塾関西支部第21回月例会の元日本海軍パイロット大野善也様による講演の動画を視聴しました。大野様は、「東京裁判を検証し、日本が侵略国家であったという汚名を晴らしたい。欧米諸国は植民地獲得競争と侵略の歴史を重ね、アメリカは米西戦争から謀略による侵略行為によって強大になった。一方日本は、日清・日露で得た権益を守るために戦い、人種差別撤廃・植民地解放のために戦った。しかし敗戦によって侵略国家だとされた。マッカーサーは後に、『東京裁判は間違いだった』と明言している。東京裁判の根拠となる管轄権についてウェッブ裁判長は答えることができず、平和・人道に対する罪は当時確立されておらず事後法による違法裁判であり、検察側に有利な証言ばかり集められ、偽証罪もなく、米軍の無差別爆撃、原爆投下に関する弁護人の発言は通訳のマイクが切られる有様で、理不尽極まりないリンチ裁判であった。戦後は国民を左翼思想で洗脳した。米国は日本人が優秀だから、今も日本が強くならないように警戒している。戦前から日本は技術力に優れ、原爆の研究や万年筆ロケットの開発もしていた。現在も固体燃料の技術は世界一、人工衛星技術も高度であり、青色発光ダイオード発明はノーベル賞に匹敵し、iPS細胞の開発等々、先端技術は群を抜いている。日本人が優秀なのは、極東の島国で優秀な人種が混血し、優性遺伝で優れたDNAを伝えたからだ。日本人は識字率が高く、教育においても教養においても素晴らしい。敵兵をも保護する高潔な道徳性を保持している。皇室は神話時代から万世一系で続いており、その道徳は最終的に教育勅語に集約された。伝統を壊すことは歴史を否定し国を壊すことだ。安倍総理は転換期に相応しい指導者である。日本人が思う以上に世界では日本は良く思われ尊敬されている。」と、東京裁判の理不尽さや日本の科学技術の優秀さと日本人の誇りを取り戻す必要性を強く訴えられました。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄様
第29代航空幕僚長の田母神俊雄様は、「9月10日から17日までの8日間、イスラエルを訪れた。ローマに滅ぼされたユダヤ人は世界中に散ったが、キリスト教徒からいじめられてきた。第二次世界大戦ではヒトラーがヨーロッパを席巻したが、まさに宗教戦争であった。1948年5月14日にイスラエルが建国されたが、今より狭い面積での建国であった。これはユダヤ人にとって不利な和解案であったが、その2日後にアラブから攻撃を受けた。4次にわたる中東戦争でイスラエルが勝利してイスラエルの国土が広がったが、アラブ人が住んでいたところを押しのけたわけではない。謂れなき批判を受けている点で、日本とイスラエルは似ている。」「イスラエルは国を守る意識が大変強い。首相が一声掛ければ、国のあらゆる組織が動く。50日間で2,000発のミサイルがイスラエルに打ち込まれたが、短距離ミサイルであるアイアンドームで86%の敵方ミサイルを撃墜した。戦闘機はアメリカのものを買っているが、日本のようにブラックボックス化した状態では買っていない。アラブは病院や学校にミサイル基地を置いているため、攻撃に当たってはまず警告し、次に被害の出ないゴム弾で攻撃してから本格的に攻撃をする。イスラエルはできるだけ国際法に触れないようにやっている。」と、日本で報じられているイスラエルと実態との違いやイスラエルの国を守る意識の高さについて語られました。

衆議院議員 義家弘介様
衆議院議員の義家弘介様は、「森内閣のときは、私は高校で現代社会を教えていたが、当時森総理の『神の国』発言をめぐる報道を見た。日本は天皇を中心に戴き、八百万の神のいる『神の国』であるという発言の何が問題なのかと生徒に対して問いかけたが、それが後に問題となり、軍国主義だと言われた。文科政務官のときに、教科書検定に関して『特定の価値観に基づく記述を削除する』という方針を出し、中学の教科書から慰安婦問題は削除されたが、まだ高校では15の教科書のうち13で残っている。最も染めやすいのが真面目で素直な生徒達であり、そうした生徒達が左傾化した思想に染まっていくのは不幸なことである。問題なのは歴史教科書だけではない。以前高校の国語の教科書に使われていた池澤夏樹の『狩猟民の心』という文章では、日本人の心性を最もよく表しているのは『桃太郎』である、とした上で、『桃太郎』は侵略戦争以外の何ものでもないと断じている。これが戦後教育の実態である。さらに小学5年生の英語の授業を視察した際に、その授業は桃太郎の英語劇だったが、ネイティブ教師は桃太郎を“Peach boy”と子供達に呼ばせていた。桃太郎は固有名詞であり、日本の伝統的な物語であり、日本人にとって大切なものである。ネイティブ教師に抗議すると、その教師は英語にはリズムが大事だと言っていた。こうした日本の伝統や文化を無視した英語教育は百害あって一利なしである。」と、学校教育の問題点を具体的な事例を挙げながら指摘されました。

衆議院議員 田畑裕明様
衆議院議員の田畑裕明様は、「安倍政権になり、昨年12月にはじめて国家安全保障戦略が策定された。これに基づき、防衛大綱、中期防衛力整備計画も見直された。防衛費のピークは1997年の4兆9,000億円であり、過去ほぼ横ばいであった。今年度は4兆7,800億円であり、来年度は4兆8,900億円とプラス要求をしている。一方、中国の軍事費は12兆9,000億円で、ここ10年で10倍、平成になってから40倍にもなっている。」「日本の人口は、このままいけば2050年には9,700万人、うち65歳以上の高齢者が40%以上になる。地方を活性化させバランスの取れた国家を作っていく必要がある。都心部では子育て・介護環境の悪化への対処が必要であり、政府の主要機関の地方への移転も検討すべきだ。また地方に学ぶ場、働く場を創っていく。地元の富山市ではコンパクトシティを目指してきた。これからも活力のある地域を創っていき、1億人の人口を維持していきたい。」と、防衛問題や地域の活性化についての取り組みについて語られました。
塾生からは移民や留学生に関する考え方について質問が出され、田母神様からは、「安い賃金で働く労働力がほしいということが移民受け入れの背景にあるが、移民で成功している国はなく、労働力の問題は国内で解決すべきである。また、我が国には現在16万数千人の留学生がおり、その半数以上が中国人である。彼らは毎月14万2,000円支給され、往復の飛行機代、住居費、学費の負担もない。ここまで優遇するなら、日本人学生の面倒をもっと見るべきだ。」と、田畑様からは、「移民を幅広く受け入れていくことは考えていない。技能実習生の受け入れは業種も期間も限定していく。一方、IT分野などでエリート層を戦略的に活用していく。また、医療・介護では日本語教育を受けた人材を受け入れる。ただし、日本人がやらない仕事を外国人がやるという意識を日本人が持つことは危険である。」と、それぞれの考え方を披露されました。さらに、衆議院議員の原田義昭様は、「技能実習生の受け入れが進んでいるがその7割が中国人である。日本の産業を維持するためには労働者が足りないが、無尽蔵に受け入れるべきではない。高度成長期でも人口が増えたから経済が成長したわけではない。人口が減少しても経済が成長するよう生産性を高めていく必要がある。」と人口減少下でも経済が成長するような取り組みの必要性について語られました。
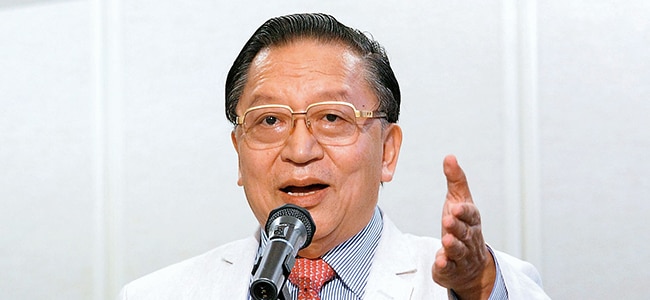
桐蔭横浜大学教授 ペマ・ギャルポ様
桐蔭横浜大学教授のペマ・ギャルポ様は、「8月30日から9月3日までインドのモディ首相が来日した。まず京都を訪れたのは、日本の成功からだけでなく、高度な精神文明や伝統から学びたかったからだ。『特別な』グローバルパートナーと言ったが、心と心が繋がったという意味で『特別』なのである。これまで日本とインドは一度も戦争したことはない。また日本は他のアジアの国々とも戦争したことはない。日本は各国の宗主国と戦ったのであって、アジアの国々と戦ったわけではない。」「日印首脳会談についてNHKは偏った報道をしている。今回原子力協定について結論は出なかったが、外務省の中に慎重論があり、平和運動勢力の妨害もあった。また、外務・防衛の閣僚級協議の創設が見送られた。インドの中にも日本と同様にチャイナスクールがいる。」「モディ首相は選挙期間中、中国を『18世紀の帝国主義』と呼び、インドの領土を侵略させないと牽制した。インドの伝統的な外交はどことも同盟を結ばないことである。日本に対しては憲法9条があるため、同盟を結んでも日本がどこまでできるか疑問を持たれている。中国はモディ首相に対しては低姿勢で臨んでいる。習近平はインドを訪問したが、モディ首相が自ら出向いたのは日本が初めてである。インディラ・ガンジーやネールは極めて親日的であった。1951年のサンフランシスコ講和条約にインドが調印しなかったのはその内容がおかしかったからであり、翌年対等な条約を結んでいる。日印関係がせっかく盛り上がってきたのだから、中国の野望に対抗するために、手を結んでいくことが重要だ。日本とベトナム、インドが手を結び、アジアの問題はアジアで解決するべきだ。インドは東部開発を日本に依頼した。これは中国との国境問題があるからである。ここでは民間の力が必要だ。インドでは親日に与党も野党もない。アジアでの軍事競争が激しくなっているが、そうさせているのは中国である。ここで日本が動かなければならない。」と、中国に対抗していくために日印関係の重要性を訴えられました。

軍事ジャーナリスト 鍛冶俊樹様
軍事ジャーナリストの鍛冶俊樹様は、「世界の空軍関係者が注目しているのは尖閣である。中国のスホーイ27と日本のF15が一戦を交えるのはいつかという問い合わせがよく来る。F15はレバノン紛争のときにアメリカからイスラエルへ供与され、シリアに対してはソ連からミグ23が供与された。このときミグ23の80機全機がF15に撃墜されたが、F15は無傷だった。さらに湾岸戦争やイラク戦争でもF15はミグ25、ミグ29を撃墜した。しかしスホーイ27とは戦ったことがないからどちらが勝つか注目されている。中国は5月、6月に戦闘機が異常接近してきたが、あれは危険運転のようなものである。日本の自衛隊の方がはるかに技量は高い。中国はロシアの戦争機をライセンス生産しているが、まだ技術力が低い。そのためパイロットの技量も上がらず、それが中国空軍の弱点である。」と、戦闘機を巡る軍事情勢について語られました。

勝兵塾事務局長の諸橋茂一様
勝兵塾事務局長の諸橋茂一様は、「先日21名で、戦跡巡りツアーでペリリュー島を訪れた。パラオ共和国は人口2万人であるが、2年前に中国漁船が領海侵犯をした際に停船命令に従わなかったことから攻撃して沈めた。こうした国際法に則った対応をなぜ日本ができないのかと思う。ペリリュー島の戦いでは、当初米軍が3、4日で片付くと言っていたものを、中川州男大佐率いる日本軍は72日間の壮絶な戦いの末、1944年11月24日に『サクラサクラ』の電報を最後に打電し、玉砕した。米軍が上陸した9月15日にはペリリュー島の戦い70周年の記念式典が米国主催で行われ、米国からはパラオ大使や海兵隊の准将、軍楽隊、生き残りの元米国軍人が参加したが、日本からは元日本軍人の土田喜代一さんとそのお孫さん、そして我々だけであった。海兵隊の軍楽隊によりまず君が代が演奏され、我々一行は壇上で起立して斉唱した。」と、ペリリュー島訪問の報告をされました。
最後に塾長より、「8月15日には靖国神社に参拝したが、今年は例年にないくらい多くの人々が参拝し、特に若者や女性がたくさんいた。靖国神社からはこれまでの貢献に報いたいとして、Apple Townへ広告を出したいという申し出を頂いた。来月号に掲載されるので見ていただきたい。23年間に亘ってApple Townを発刊し、22年間以上に亘りエッセイを書き続けてきた。6年前には懸賞論文制度を始め、その後、世の中が変わり、朝日が謝罪会見をするまでになった。その一翼を担うことができたと思う。田母神騒動がなければここまで保守化が進まなかったのではないか。」と、これまでの塾長の取り組みと日本の保守化について振り返られ、25日に開催される田母神様の出版記念パーティーのご案内をして、会を締め括られました。
研修会の後は、レストラン「ラ・ベランダ」に会場を移して懇親会が行われ、研修会での流れのまま活発な議論が尽きず、予定時間を大幅に超過する盛況ぶりでした。


