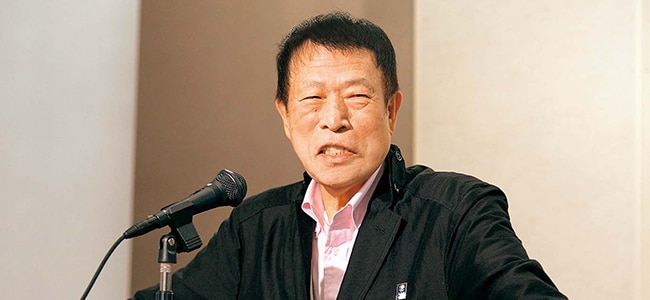
塾長・最高顧問 元谷 外志雄
勝兵塾第74回月例会が、7月20日(木)にアパホテル〈東京潮見駅前〉で開催されました。冒頭のアパグループ元谷外志雄代表による塾長挨拶では、「今月号のエッセイは『先の大戦は日本を叩く白人国家の謀略だった』という内容だ。日露戦争で日本がロシアに対してまさかの大勝を収めたことで、アメリカはオレンジ計画を策定し、日本を戦争に追い込んだ。しかし、19世紀に松前藩に捕まったゴロブーニンが、『日中両国が手を結べば百年といわず白人国家の最大の脅威になる』と報告しており、この頃には日本の台頭が白人国家にとって脅威だという認識があった。日本は先の戦争には負けたが、世界から植民地はなくなり、人種平等が実現した。白人国家が植民地支配を守るために日本を叩いたが、結果として植民地を失ったのである。」と、今月号のエッセイのエッセンスを紹介され、「アパグループの躍進振りに注目が集まっているが、それは現在すでに開業しているホテルを見ての評価であり、現在設計・建築中のホテルが全て開業すれば評価はさらに高まるだろう。しかし、他社のホテルもどんどん増えて、すでにオーバーホテル現象が起きつつある。この先、ホテル業界も百花繚乱から寡占化へ進んでいくだろう。オリンピック後にはさらに厳しいオーバーホテル現象が起こる。アパは頂上戦略初期の土地代も建築費も安い時に開発したホテルが満室稼働で、高い収益力に繋がっているが、後から高い土地代に高い建築費でホテルを開発しているところはこれから苦しくなるだろう。そうしたホテルを買収して断トツの日本一を目指す。6月30日にランドマークホテルとなるアパホテル〈国会議事堂前駅前〉の起工式が行われ、多くの国会議員の方々にもご出席頂いた。日本の中枢と言える立地にホテルがオープンすることはアパのブランドアップに寄与するだろう。」と、アパグループの事業展開について語られました。

衆議院議員 今村雅弘様
衆議院議員の今村雅弘様は、「7月20日は、本来は『海の日』である。ここ潮見の近くの越中島にある東京海洋大学に明治丸が保管されている。明治丸は、明治7年にイギリスで建造された灯台巡視船を明治政府が購入したものである。明治天皇の東北巡幸にも供され、1876年7月20日に横浜港に帰港したことを記念して、1941年に7月20日が『海の記念日』に制定されたことが、現在の『海の日』に繋がっている。しかし、平成15年の祝日法の改正によって、『海の日』が7月の第三月曜日となったことで、本来の意味が忘れられている。当時、イギリスとの間で小笠原諸島の領有問題が起こり、日英が現地調査を行うことになったが、明治丸は最新鋭で船足が速く、イギリス船より早く現地に到着して調査を進められたことで、小笠原諸島は日本の領土になった。この明治丸を保存するための運動を起こし、現在は重要文化財に指定され、補修費用も国が負担した。明治政府がまだできたばかりの時に、なぜ高価な船を買ったのか。それは日本が海洋国家、通商国家として生きていくためには、灯台巡視船が必要だと考えたからである。我々も国を守っていくために知恵を出し、力を合わせていかなければならない。そうした意味でも、是非皆さんにも明治丸を見てもらいたい。」と、「海の日」に因んだ歴史を紹介されました。

陸軍中野学校出身で、桜花梅香懇話会会長 牟田照雄様
陸軍中野学校出身で、桜花梅香懇話会会長の牟田照雄様は、「『桜花梅香』は中国語の発音で『インフォメーション』である。太陽、地球、月の中心軸が一直線になるのが72年に一度で、『72年蘇生の周期律』と言われる。今年は終戦から72年である。1995年には阪神・淡路大震災が起こったが、その72年前の1923年に関東大震災が起こっている。旧ソ連はコミンテルンによる建国の72年後には崩壊し、朝鮮労働党は創立72周年にICBMの発射を成功させた。そして中国は、2期目を迎える習近平政権の任期中に72年周期が来る。中国共産党政権や朝鮮労働党はコミンテルンとスターリンによって生まれた。金聖柱(後の金日成)はコミンテルンに推薦され、北朝鮮の最高指導者となった。金聖柱は、元々は東北抗日連軍の下級幹部に過ぎず、抗日パルチザン闘争で活躍した金日成は彼の先輩であり、全くの別人である。中国は7月7日に盧溝橋事件80周年を盛大に祝い、盧溝橋事件は『日本侵略者の挑発』と宣伝した。12月は南京事件80周年である。盧溝橋事件はコミンテルンが中国共産党を指導して日本軍と国民党政府軍、双方に対して発砲させた謀略であり、周恩来も共産党による謀略であったことを認めている。東北抗日連軍の金日成(金成柱)は1937年に労働党副委員長の朴金喆に盧溝橋事件は『コミンテルンの指示で中国共産党が挑発』と明言している。こうした証拠はたくさんあるが、中国の教科書や抗日記念館では『日本軍による挑発』と教えている。コミンテルンの砕氷船理論では、ドイツをフランス、イギリスと、日本を蒋介石の中国と戦わせて疲弊させ、最後にアメリカを参戦させて日本とドイツを敗北させたのちに、ドイツと日本が支配した地域と日本、ドイツ両国を共産党陣営が支配することを目指していたが、最後の部分を除けば、その通りに進んだ。戦争には武力戦と秘密戦がある。秘密戦は諜報戦でもある。今はサイバー戦、歴史戦、心理戦が重要であり、代表が主張されるように、中央に宣伝省のような組織を設置しなければならない。対外的な宣伝費は、中国が1兆円であるのに対して日本は350億円に過ぎない。国連の公用四カ国語をはじめ、多数の言語で誤った思想を正していく必要がある。サイバー攻撃は核兵器を自爆させることもできるが、防衛不能である。日本もサイバー戦力の強化をすべきである。」と、コミンテルンの指導を受けた北朝鮮や中国の歴史の真実を語られるとともに、歴史戦やサイバー戦の重要性を訴えられました。

衆議院議員 武藤貴也様
衆議院議員の武藤貴也様は、「安保法制特別委員会が行われていたときに、SEAL‘sの反対運動に対してツイッターで利己的だと批判したら、マスコミから総攻撃を受けた。マスコミは一部を切り取って報道するものであり、今の日本の政治を歪めている張本人である。私は国際協力の必要性を訴えたのである。私達が豊かな暮らしをしているのも国際社会の協力の上に成り立っている。シーレーンを通過する船の8割は日本船であるが、これを海賊などから守っているのは各国の軍隊である。つまり各国が助け合って発展の基礎をつくっているのである。憲法を理由にこうした国際協力を認めないことに対して利己的だと言ったのである。しかし、マスコミは一部を切り取って報道し、反論を許さない。7月7日には青森で中国船が領海侵犯したが、ほとんどのマスコミが報じていないのが現実である。これに対しては国民運動を起こしていくしかない。中国の軍拡とロシアの再興で国際秩序は変わりつつある。アメリカがスーパーパワーであった時代は日米同盟だけでよかったが、これからは日米同盟一辺倒で良いのか議論を始めなければならない。同時に憲法の議論も必要である。紙に書かれた文字を変えるだけでなく、その前提となる議論にも決着をつけなければならない。その議論とは、まずは過去の歴史認識である。先の大戦が侵略戦争であったのか自衛戦争であったのかである。次に憲法の位置付けである。憲法は柔軟に解釈すべきであるという考え方もある。また国家の理想を盛り込む必要もある。さらに、日本が国際社会でどうしていくのか、国連中心主義で良いのかという議論もある。」と、マスメディアの報道姿勢の問題を指摘されるとともに、憲法の議論の前提となる重要な論点を示されました。

大阪市立大学名誉教授・経済学博士 山下英次様
大阪市立大学名誉教授・経済学博士の山下英次様は、「デイヴィッド・ケイは言論の自由に関する国連特別報告者であるが、彼が2016年4月に発表した暫定報告の内容が事実に反するため、日本の民間団体から計5本の反論が出された。これは前例のないことである。今年の5月に最終報告書の草案が発表されたが、これに対して翌日には日本政府から詳細な反論が出された。6月12日に最終報告が行われたが、同日日本政府代表部井原純一特命全権大使の反論が行われ、16日には私もスピーチの機会を得た。NGOとしてのスピーチであったが、NGOの数が多いため、割り当てられた時間は90秒だった。D・ケイを日本に呼び込んだのは、日本の左翼の人権活動家や、アメリカの反日の急先鋒であるコネティカット大学教授のアレクシス・ダッデンらである。前例のない反論文を受けて、D・ケイの論調はトーンダウンしており、暫定報告にあった『(日本の言論状況は)かなり広い領域において、危険なほどに状況は急速に悪化している』という極端な文言は消えた。国連中心主義というものを日本人は誇りに思ってきたが、これを止めなければならない。国連とは連合軍のことであり、国連憲章には未だに旧敵国条項がある。また、国連には各国から左翼がたくさん来ている。日本の拠出金は10%弱で世界第二位であるが、政府も民間もいかに国連を利用するかを考えるべきである。」と、ジュネーヴ国連人権理事会でのD・ケイ氏の報告を巡る経緯を説明され、国連中心主義の問題点を指摘されました。

サー中松義郎博士

名城大学講師 久野潤様

元出光興産・保護司・家庭裁判所調停委員 奥本康大様

ノーネスLLP代表執行役兼CEO 平山秀善様
最後に塾長は、「『Apple Town』は今月で第324号となり、27年間発刊してきた。エッセイは第300回で、ちょうど25年連載を続けてきたことになる。懸賞論文は今回で第10回だが、今回から最優秀賞の賞金が500万円に増額された。8月31日が締め切りなので、是非応募して頂きたい。この懸賞論文制度を始めたことによって、日本人が覚醒し、日本の保守化に貢献してきた。」と、懸賞論文への応募を呼びかけられて会を締め括られました。


