第173回 勝兵塾月例会レポート
公開日:2025/11/26

株式会社KBM代表取締役会長 諸橋茂一勝兵塾事務局長
冒頭に株式会社KBM代表取締役会長の諸橋茂一勝兵塾事務局長は、まず55年前の11月に自決された故三島由紀夫氏に哀悼の意を表されたのち、「70年前の11月に自民党が結党されたが、立党宣言には自主憲法制定が掲げられていた。しかし、いつの間にか表現が憲法改正に変わっている。両者は意味が大きく異なっており、自主憲法制定のロジックでは現憲法の成立過程や内容が、大日本帝国憲法やハーグ陸戦法規の占領国統治に関する条文に違反しており、その無効決議を行った上で新憲法案を策定する形になる。しかし現憲法96条に則って憲法改正を行うと現憲法の正当性を認めたことになり、現憲法の無効性を主張できなくなってしまう。やはり現憲法では有事の際に日本の領海・領空・領土、天皇を中心とする国家体制を護り、合わせて日本国民の生命・安全・財産を護ることは難しく、自民党立党の原点に戻り真剣に考え直す必要がある。」とお話しされました。

衆議院議員 西村康稔様
衆議院議員の西村康稔様は、「過去に経産省から石川県庁の商工課長に出向していた縁もあり、元谷塾長ご夫妻には人生の師として長年ご指導頂いている。トランプ大統領が誕生した背景には、アメリカの国力が相対的に低下し、国内の労働者が非常に疲弊している中で、『アメリカ第一』を掲げ、保護関税で中国から守る政治家が支持される土壌があったことがある。軍事的にもアメリカは、『世界の警察』から撤退しており、日本も『自分で自分の国を守る』必要性に迫られている。私は2回前の総裁選に高市氏の推薦人代表となっており、一貫して高市首相誕生に奔走していたが、高市政権もこうした流れの中で誕生した。安全保障では、アメリカ以外の国々との連携を深めていくため、特に故安倍元首相が提唱した『自由で開かれたインド太平洋』を日本が主導し、アジアのリーダーとしてスピード感を持って安全保障に取り組むことが求められている。また、GCAPと呼ばれる日英伊共同開発の次期戦闘機開発を行い、他国へのライセンス生産として展開していく。これに関連して、防衛装備移転三原則と運用指針によって定められた現行ルールにより、非戦闘目的の『5類型』に該当する防衛装備品のみ輸出を認めてきた状況を変更することが必要である。次に経済政策について、アベノミクス以降の金融緩和と財政出動の結果、日本の税収が過去最高を記録しているが、その背景には、物価高と円安による国民生活の負担増や企業収益の増加がある。私はこの税収増を、補助や給付を通じて国民に還元すべきだと考えている。故手塚治虫氏の新作をAIで作るプロジェクトを実施したが、すぐに完成したわけではなく、試作品を何度も修正し、壁打ちを繰り返して推敲を重ね完成度を高め、2023年に発表することができた。つまりAIの技術に頼るだけではなく、それを使いこなし、よりよいものを作り上げる人材が必要である。私は自民党総合エネルギー戦略調査会長であるが、火山大国である日本には、地熱発電のポテンシャルがある。その他、自民党の財政改革検討本部長、選対委員長代行として、マクロ経済政策の骨組みを作っていくとともに、連立政権との関係や選挙対策も徹底しながら、高市政権をしっかりと支えていきたい。」と、今後の意気込みについてお話しされました。

神戸市会議員 上畠寛弘様
神戸市会議員の上畠寛弘様は、「非核神戸方式と呼ばれる、神戸市議会が50年前に決議をした『核兵器を積んだ艦船を神戸港に入港拒否する』という市議会暴走とも言える方針についてお話しする。これは当時の宮崎辰雄市長のもと、満場一致で決議されたものであるが、神戸港へ入港する外国軍艦に対して『非核証明書』の提出を求める独自制度である。実質的にアメリカを名指しにした制度で、証明書は軍事機密の提出に等しく、米艦船はこの要請を拒み続けた。阪神・淡路大震災の時すらも入港することができず、神戸港以外からの物資支援に限定されたことで、即応的な支援ができなかった。一方で同じ宮崎市長の在任時に、中華人民共和国初の友好都市として、神戸市と天津市が友好都市となり、王子動物園が中国からパンダをレンタルした。さらに、神戸港と武漢新港はパートナーシップ港の協定を締結しており、歴史的に反米、親中なのが神戸市である。私は神戸市会議員として3期目を迎えてから、学校給食からの中国産食材の排除や、武漢港との協定の破棄、神戸市の上海事務所廃止、さらには神戸市の税金で人民解放軍のOBが天津事務所で雇用されていた問題を明らかにするなど、脱中国の施策を進めている。しかし、神戸は左派から非核神戸方式の聖地とされており、かつては苫小牧市や高知県など各地でも同方式の推進に向けた動きがあった。本来は安全保障に対して一自治体が介入すべきではないと考えるし、非核神戸方式はあくまでも地方議会の決議に過ぎず、国法上の根拠はないばかりか、日米同盟への実質的な妨害になり得る。そこで私は昨年11月に、アメリカ総領事と神戸市港湾局の会談を設定し、そこで総領事から『米軍艦隊は既に戦略的核兵器を搭載していない』旨の説明があった。これは非核証明書よりもはるかに意味のある事実確認であり、さらに米軍の海軍公文書、ブッシュ・レーガン両大統領の非搭載方針表明も論拠に、翌12月神戸市議会の一般質問で、神戸市がこの事実を把握している答弁を引き出した。それを根拠に2025年3月、実に50年越しで米掃海艦ウォーリアが非核証明書を提出せずに神戸港へ入港した。行政法上、先例ができた場合はその先例に従う必要があり、各国を平等に扱う必要があるため、米軍は神戸港に非核証明書なしで入港できるようになった。議員1人の力でも、頑張れば50年間の悪しき聖域を打破できることを皆さまに知って頂きたい。」と、市議会での活動についてお話しされました。

元衆議院議員、公認会計士 桜内文城様
元衆議院議員、公認会計士の桜内文城様は、「2013年に一度勝兵塾で講演した際は従軍慰安婦の問題について話した。当時、自称歴史学者の吉見義明氏の著書で慰安婦を性奴隷と主張していたことを私が否定したことで、彼から名誉毀損訴訟を提起されていた。しかし、奴隷については1926年に国連が採択した奴隷制度廃止補足条約に明確な定義があり、この定義に慰安婦は当てはまらないということを論点とし、勝訴することができた。本日は、先月出版した自著である『マクロ会計学』をご紹介したい。これは従来のマクロ経済学ではなく、会計学の複式簿記の観点からマクロ経済を再構築する試みの本である。副題を『貨幣と資本蓄積』としているが、これは既存のマクロ経済学の体系が、経済の根幹であるマネーを適切に扱えていないという問題意識から出発している。マクロ経済学が前提とする『一般均衡理論』は、マネーが存在せず、物々交換だけで需給が均衡するという理論であり、現代の銀行システムが生み出す信用創造という仕組みを扱うことができない。数学的な論理として、マネーとして生まれている銀行会計上の負債については、複式簿記を用いて説明する必要がある。そこで本書ではマクロ会計学として複式簿記を用い、マネーも含めた経済全体を適切に把握し、一国経済全体の資本である国富をどのような財政政策・金融政策で増加できるかを理論的に解明している。財務省の予算編成の仕組みは現金主義として未だに歳入と歳出のバランスを取ることに執着しているが、それでは必要な投資や消費税の減税を適切に実施することはできない。国富を増やすためのメカニズムとして、主に二つのルートがある。一つは銀行の貸し出しを通じた適切な投資であり、もう一つは財政赤字である。財政赤字は一見悪いものと思われがちだが、財政赤字が増えるほどマネーストックという貨幣の総量が増える。つまり、財政政策が貨幣の総量をコントロールできる機能を持つことを複式簿記から明らかにしている。複式簿記は過去の決算だけでなく、予算ベースの数値を適用することで未来のシミュレーションにも活用できるため、現実の経済政策の効果を正確に予測できることもこの本で触れている。本日ご臨席の西村康稔氏は財政改革検討本部長を務められているとのことで、ぜひ日本の経済を真に強くするための政策立案、予算編成をお願いしたい。」とお話しされました。

慶應義塾大学名誉教授・公益財団法人アパ日本再興財団理事 塩澤修平様
慶應義塾大学名誉教授・公益財団法人アパ日本再興財団理事の塩澤修平様は、「経済学的に一種のフローであるGDPと、国民の消費と投資というストックをいかに結び付けていくかという道筋についてどのようにお考えか。」と質問され、桜内様は「GDPは一国の特定期間中の取引高であり、会計的には粗利に相当する。ピケティの『21世紀の資本』の中に資本収益率という概念があり、一国経済全体の資本を増やせば名目GDPも連動することが分かる。固定資産を増やす投資が必要であるが、一方で外貨建ての対外純資産を増やしても国民への付加価値には当たらず、国内投資を積極的に行う必要がある。シンガポールやマレーシアでは投資税額控除制度によって戦略分野への税額控除を促進しており、高市政権にも防衛などの特定分野に同様の戦略を期待したい。」と答えられました。

元陸上自衛隊富士学校・衛生学校研究員、有事・軍事医療ジャーナリスト 照井資規様
元陸上自衛隊富士学校・衛生学校研究員、有事・軍事医療ジャーナリストの照井資規様は、「現在の国際情勢は核兵器が現実に使われる時代に入っており、日本は防衛を整えるための経済力を高める必要がある。また問題なのは、日本の自衛官に核兵器に関する知識が不足していることである。これは非核三原則により、自衛官が核兵器をタブー視してきたためと思われるが、被爆国であるからこそ自衛官は核兵器に詳しくなければならない。現代の核兵器は小型化が進み、爆発力を抑えてEMPと呼ばれる電磁パルスや放射線を強化したものが主流であり、これは兵器の使いやすさを高め、高高度核爆発によるEMP攻撃で電子機器を無力化する戦略的な兵器である。こうした攻撃に強いのが人間であるため、ドローンやAIの時代であっても各国で徴兵制が残っており、人的資源の必要性は依然高い。日本は国後島と択捉島の間にある国後水道と、与那国島と台湾の間にある海域に地政学的リスクを抱えている。いずれも原子力潜水艦を通すことができるため、ロシア・中国がその海域を狙っている。日本はソ連崩壊前、自衛隊演習で想定する敵国として、ロシア・中国・北朝鮮・アメリカを挙げていた。これは在日米軍が敵となるケースも想定しなければならないということである。しかし、アメリカと他3国の違いは、戦争に負けたら日本に住むことはできなくなるということである。また、企業もこうした兵器による停電や通信遮断によるリスクへの対策、特に人的教育が重要であるが、業種によっては一斉訓練ができない会社もある。そこでJAL・ANAは誕生日を迎えたCAに随時訓練を受けさせることで、必ず最新の訓練を受けたスタッフを配備できるようにしている。またディズニーリゾートでは毎日短時間の訓練を行うことで災害時に常に対応できるようにしており、安全安心を企業の根幹として重視している。一方で、陸上自衛隊では災害時に必要な、けが人の診療記録の体制が整っていない。そこで現在、航空自衛隊と陸上自衛隊の様式を合わせ、多言語にも対応した緊急の治療体制を整えるため、防衛大臣からレクチャーを依頼されており、来月以降『石川県モデル』として展開していく予定である。自衛隊は人手だけでなく装備も不足しており、防衛費を増額しても必要なところへ投資していない。防弾ベストに使用されている繊維は過半数が日本製であるが、そうした日本の優れた技術を用い生産を拡大し、経済的に豊かになって防衛対策を万全にする必要がある。」と日本の防衛体制の危機についてお話しされました。

敬愛大学名誉教授、IPU環太平洋大学国際経済経営学部教授 藪内正樹様
敬愛大学名誉教授、IPU環太平洋大学国際経済経営学部教授の藪内正樹様は、「現代の戦争は軍産複合体の思惑によるビジネスの側面が強いとは思うが、その点についてどのようにお考えか?」と質問され、照井様は「現代の戦争は、各国が各々の兵器を造るわけでなく、軍産グローバル企業が兵器を造るため、一つの戦争をやめるには別の戦争をやるしかない。彼らの動きを理解するにはカネの流れを追う必要があるが、資源について考えると、北極海が重要であり、東側のベーリング海峡を巡った争いが見られる。次の戦争の火種、武器の売却先は、アフリカ大陸が最も有力であるが、そこへの航路もやはり北極海経由である。つまりベーリング海峡を掌握する国が主導権を得ることができる。そこで、先ほど述べた国後水道と台湾・与那国島の海域とその先の日本海溝が原子力潜水艦の待機場所として有力であり、日本は南北に危険な場所を抱えた状態にあることを国民は自覚する必要がある。」と答えられました。
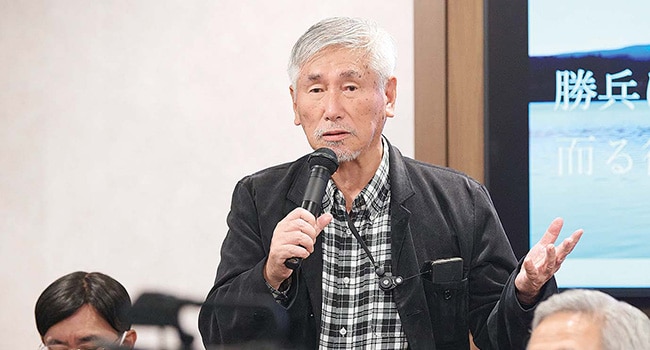
英霊の名誉を守り顕彰する会会長 佐藤和夫様
計画哲学研究所所長・工博・元早稲田大学客員教授・新しい日本を創る会代表の三輪真之様は、「ウクライナやガザ地区の報道で、民間人の犠牲だけを報じる姿勢に疑問を感じる。軍人の死を軽視していないか。若い世代に国防について問うと、自衛隊の人に頑張ってもらえばいいという言葉が返ってくる。軍人の命は軽視してもよいのかという問題提起が、国防を語るうえで必須ではないか。」と質問され、英霊の名誉を守り顕彰する会会長の佐藤和夫様は、「私も元自衛官として、自衛隊が命がけで国を守ることに対する国民の理解について疑問を抱いている。戦後の歴史観から、日本は軍ひいては自衛隊を悪とする見方がいまだに根強いが、国民が自衛隊を応援し支持していく、彼らの尊厳を保つことが重要であると考える。」と答えられました。

評論家 橋本琴絵様
評論家の橋本琴絵様は、「夫婦別姓について、歴史的に日本が夫婦の姓についてどのような慣習であったかのお話しをしたい。夫婦別姓推進派が以前の日本を夫婦別姓とする主張があるが、法務省のHPにも夫婦別姓の歴史的根拠として明治初期の太政官指令を例示している。まず太政官指令についてだが、当時の戸籍法では地方役場から県庁・内務省を通じ太政官に戸籍に関する質問があり、それに対する回答例が太政官指令である。法務省は明治9年3月17日の太政官指令で『婦女が嫁ぐ時は別姓で良いが、夫の家を相続する場合は同姓』でなければならないとして夫婦別姓を論じているが、この『婦女が嫁ぐ時』というのは、妾が嫁ぐ場合や夫以外の彼氏や外国籍の人に嫁ぐ場合の話をしており、国民をだましている。他の太政官指令を見ると、結婚で夫婦どちらの苗字もなく、新しい苗字にしたいという人に対し、太政官は男子の苗字に従うべきこと、明確に婚姻する場合同姓にするべきことと回答している。また法務省は国会答弁でも、江戸時代には夫婦同姓制度は存在せず夫婦別姓であったと発言しているが、これも嘘であり、実際の私の親族の戸籍を見ると、天保時代に女性が入籍した際、夫の姓を名乗っていることが分かる。夫婦別姓制度の推進が、日本の伝統的な氏の文化や家族制度を破壊する行為であることは周知のとおりだが、日本の氏の歴史は中韓との違いが大きい。日本には墾田永年私財法の時代から、苗字が土地の私有権を保証している文化があり、苗字という言葉も苗木を植えることに由来している。これは家族の継続を意味する『ファミリーネーム』の意味を持っている。一方で、中韓には土地所有権の永続的な保証がなく、血族を表すカバネ、『ブラッドネーム』としての名字しか存在しないため、女性は結婚しても苗字が変わらないのが自然である。また子どもの場合、選択的夫婦別姓制度を導入すると、子どもの苗字はその際に適宜考えるということになるが、これではファミリーネームでもカバネでもない、ただのあだ名にまで成り下がってしまう。そのような歴史的背景の違いを考慮しない文化の輸入は、日本の伝統的な家族制度や国家社会を破壊するものであり、こうした流れを助長する法務省の誤った歴史の拡散、情報浸透は許されるものではない。」と、日本の伝統を破壊する夫婦別姓制度についてお話しされました。

スタンフォード大学フーバー研究所教授 西鋭夫様
スタンフォード大学フーバー研究所教授の西鋭夫様は、「高市首相の誕生が決まった際のトランプ大統領の囲み取材を見ていると、しばらく見ていないような満面の笑顔だった。対照的に、その少し前に石破前首相がホワイトハウスで晩餐会をした際に、トランプ大統領は何度も“I like Shinzo.”と話され、石破氏の顔が引きつっていたことが印象的だった。トランプ氏はそんな安倍氏の弟子である高市首相を応援しており、日本初の女性総理大臣として大きく日本の空気が変わっていくことを期待している。」とお話しされました。
