第170回 勝兵塾月例会レポート
公開日:2025/8/27

塾長・最高顧問 元谷 外志雄
勝兵塾第170回月例会が、8月21日にアパグループ東京本社で開催されました。
冒頭に塾長は、「本日は東京で170回目の勝兵塾月例会となる。テレビや新聞では中々伝えることのない『本当はどうなのか』ということを知る機会として、東京・大阪・金沢の3会場で毎月勝兵塾を開催している。講師からのお話だけでなく、参加者の方からの質問も積極的にしていただき、活発に意見を交換できる場となることを期待する。」と述べました。

衆議院議員 小森卓郎様
衆議院議員の小森卓郎様は、「私は現職に就く前に国家公務員として、防衛省・財務省で計5年程度安全保障関連の仕事を経験し、現在は自民党内で、『南西諸島の国民保護強化プロジェクトチーム』事務局長を担当している。安全保障上の懸念が発生した際に、住民や観光客を先島諸島から九州の各県や山口県に移動させる、有事を想定したシミュレーションが進んでいる。日本では長い間、有事の対策について考えること自体が不適当であり平和的でないという風潮があったが、これは勝兵塾の由来である『勝兵は先ず勝ちて而る後に戦いを求める』と真逆の考えである。先島諸島は5市町村、11万人からなる島々であるが、これに約1万人の入域者を加えた12万人を6日間で避難させる計画を昨年度に立案し、現在詳細を検討中である。例えば石垣市については山口県、福岡県、大分県の3県にまたがって避難するような形となるが、コミュニティ毎にまとまった避難先となるよう配慮している。受入れ側としても、例えば世帯人数に応じてホテル・旅館へ避難者を振り分けられる様なプランニングを検討している。国としては受入れ側の県がどこまで主体的にコミットしてくれるかを懸念していたが、自県の空港を提供していただけるなど大変ありがたい申し出があり感謝している。能登半島地震の際、政府の現地対策本部副本部長として対応に当たっていたが、特に輪島市や珠洲市など分断された地域で、事前の準備なしに避難対応を行うことの難しさを痛感しており、その点からも事前に避難計画を策定することが大事と考えている。関連して特定利用空港・港湾について話したい。これは平時には安全保障用ではない空港・港湾であっても、臨時に自衛隊や海上保安庁が使用できるよう、3年前に始まったプロジェクトである。また必要な投資が各省庁より補助されるため、自治体にとってもプラスである。限られた国力で有事に対応するためには民間の施設を適宜活用しながら対応することが重要であるが、残念ながら具体的な有事対応について戦後長い間、日本は思考停止状態で具体的な計画を定めていなかった。こうした地道な活動をしつつ、将来的には改憲勢力が国会発議に必要な3分の2をクリアし、憲法改正という目標を達成しなければならない。最後に特定利用空港・港湾について、沖縄県については国・市管理の施設しかなく、県管理の施設は含まれていない。これはご存知の通り県知事がこうした整備に消極的であるためであり、この状況を変えるためにはやはり選挙が大事である。」と、有事に備えた計画の重要性をお話しされました。

英霊の名誉を守り顕彰する会会長 佐藤和夫様
英霊の名誉を守り顕彰する会会長の佐藤和夫様は、「8月12日に総理官邸前で、稲村公望氏や藤岡信勝氏、矢野義昭氏らが参加して、戦後80年の石破談話断固阻止、安倍談話の上書きを許さないとする集会を実施した。実際には談話はなかったものの、全国戦没者追悼式で13年ぶりに『反省と教訓』という言葉を使い、戦争への反省に言及した。また降伏文書調印日である9月2日にメッセージを出す可能性があると伺っている。しかし、日本が既に矛を収めていたにも関わらずソ連が多くの住民を殺しシベリアに抑留した、倫理に反する行為が行われていた9月2日に、あたかもそれを認めるかのようにメッセージを出すことの意味について、自民党内でどのようにお考えか。」と質問され、小森様は、「ひと言でいうと、70周年の安倍元首相の談話に付け加えることは何もないと考えている。当時様々な方から安倍元首相がヒアリングを行い、多方面に配慮した談話となっている。また今月、自民党内で両院議員総会があった際にも談話について話が及び、新しいものを出すべきではないという意見が複数の議員から出ていた。9月2日にメッセージを出すことはご指摘の通り、その後に続いた行為にお墨付きを与えるような印象となるため、全くの筋違いだと考えている。」と答えられました。

慶應義塾大学名誉教授・公益財団法人アパ日本再興財団理事 塩澤修平様
慶應義塾大学名誉教授・公益財団法人アパ日本再興財団理事の塩澤修平様は、「先ほどの計画以外に、具体的に有事を想定したシミュレーションやプロジェクトがあるか。」と質問され、小森様は、「体系立てているものは本日お話した内容が最も具体的な計画である。一方で、具体的な交戦法規が自衛隊に存在しない中ではあるが、有事の際に法律に縛られず合理的な軍事行動が取れるような体制は自衛隊内で整えられている。また自衛隊員と防衛省の関係性も良好になっており、新型コロナの際も統合幕僚長の下でプロジェクトチームが設けられ、看護師や医者の方を含め、自衛隊に真っ先に臨機応変に対応していただいた。こうした関係性をベースに、有事の際の体制を整備していきたいと考えている。」と答えられました。
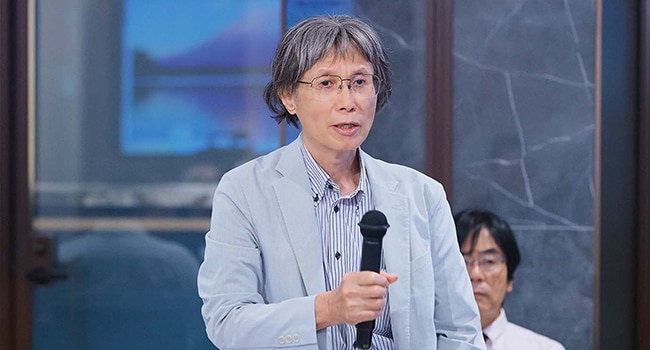
日本戦略情報研究所所長 林文隆様
日本戦略情報研究所所長の林文隆様は、「沖縄の県知事や沖縄本島の県民は避難計画や特定利用空港・港湾についてどのように考えているのか。どうしても他人事のような印象を受けてしまう。」と質問され、小森様は、「先ほど特定利用空港・港湾に県の施設が含まれていない、消極的であるという話をしたが、実は避難計画についても先島諸島から沖縄本島を経由せずに避難する計画になっている。実際に起こりうる様々な有事のパターンに備え、本来は本島経由の選択肢も有しておきたいが、おかしな状況になっている。特に避難については沖縄県民の生命が関わってくる話なので、県が国と対立することなく協力を仰ぎたいところである。」と答えられました。

朝鮮近現代史研究所所長、「新しい歴史教科書をつくる会」前副会長 松木國俊様
朝鮮近現代史研究所所長、「新しい歴史教科書をつくる会」前副会長の松木國俊様は、「これまで『新しい歴史教科書をつくる会』として中学校の歴史教科書改善に取り組んでいたが、小学校の歴史教科書も大変なことになっている。小学社会では東京書籍、日本文教出版、教育出版の3社の教科書があるが、例えば満州事変について、日本軍が中国軍を攻撃し満州事変となったという表面的なことしか3社とも書かれておらず、日本軍が居留民を守るために駐兵していた背景は全く書かれていない。南京事件については3社とも、南京の多くの人々の生命を奪ったと断定した記述がある。日韓併合についても東京書籍に『人々の抵抗を抑え』という記述があるが、実際には国際的な条約の下に平和裏に日韓併合がなされた。また、『朝鮮の歴史は教えられず』『日本人地主の小作人になり』『工場や鉱山などでひどい条件下で厳しい労働をさせられた』『日本人の姓名に変えさせられた』などと嘘の記述が続いている。大東亜戦争についても、経緯について、日本が資源の獲得と支配権獲得を目指しアジアの地域に軍を進駐し、日本が戦場となった人々に被害を与えたと記載されており、大東亜戦争の大義であるアジア解放について、1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)で日本が独立の立役者として歓喜の声で迎えられたことは触れられていない。さらには戦争の呼称についてもアジア・太平洋戦争としており、日本の正式な呼称である大東亜戦争とは記載していない。また憲法については戦後まもなくGHQにより日本の中学校に載せられた教科書の一部を掲載している。『こんどの憲法では、日本の国が、決して二度と戦争をしないように、二つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものはいっさいもたないということです。(中略)日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。』と、日本が深く反省さえすれば世界中が平和になるというイデオロギーを今なお刷り込んでいる。現在の教科書は小学校の段階で日本人であることを恥じる気持ちを植え付けており、児童に対する精神的な虐待に等しく、彼らから勇気や正義感を奪っている。教育は児童が日本人としての精神的な基盤を養うものでなければならず、祖先の偉大な足跡を教えることで、日本人としての自信と誇りを持たせることができる。」と熱弁されました。

神道学博士、元ジャーナリスト 東郷茂彦様
神道学博士、元ジャーナリストの東郷茂彦様は、「小学校教育以外にも、例えば先日のブライアン・マークリッグの『ジャパンズ・ホロコースト』のように、大東亜戦争の悪い面をすべて日本に押し付けようとする勢力に対抗するには何が必要か。」と質問され、松木様は「『ジャパンズ・ホロコースト』への反論本が先日発刊されている。あのような内容はでたらめであるが、一見信憑性のあるような体裁をとった言説は放置しておくわけにはいかず、対抗して反論する必要がある。日本が大量虐殺をしたどころか、インディアンからフィリピン、そして原爆投下と、アメリカこそが大量虐殺を行った国であり、私はむしろアメリカン・ホロコーストだと主張するくらいの覚悟で立ち向かう必要があると考えている。」と答えられました。

一般社団法人シベリヤ抑留解明 会理事長 近藤建様
一般社団法人シベリヤ抑留解明の会理事長の近藤建様は、「ソ連によるシベリアやモンゴル強制抑留被害者の皆さまのご苦労や難儀と理不尽さを忘れず、また今後のロシアに対する日本政府の外交姿勢に毅然さを保ち続けてもらう事を願った活動として『シベリヤ抑留解明の会』を立ち上げて6年半、会員がいまだ515名ということであり、さらに一層力を入れて頑張っていきたい。これまで北朝鮮拉致問題解決に取り組まれてきた『救う会』の象徴である『ブルーバッジ』とシベリヤ抑留解明の会の『ホワイトバッジ』を1つにした『ツインバッジ』を国会議員の皆さまにつけていただくことを目標としている。8月9日に産経新聞の全国版に意見広告を掲載した。広告趣旨の一つは、8月9日を鎮魂の日として訴えていくことである。この日は長崎への原爆投下のみならず、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破って日本に侵攻した日であることを知っていただきたい。この日をきっかけに、多くの日本人がシベリアやモンゴルに連れていかれ、また中国本土から日本に帰ることなく虐殺された歴史が始まった。またいま一度、北方領土は日本の固有の領土であるとして、返還を主張したい。今月もそうした思いを胸に、街中でパンフレット配りを実施した。新しい歴史教科書をつくる会に比べるとメンバーは少ないが、地道にでも自分の思いを主張していく。これからも日本の誇りを取り戻すために、相手が中国・北朝鮮・ロシアであろうと勇気を持って行動していきたい。」と決意表明を含めお話しされました。

岡崎研究所特別研究員、「月刊日本」客員編集委員 稲村公望様
岡崎研究所特別研究員、「月刊日本」客員編集委員の稲村公望様は、「今月、プーチン大統領が米露首脳会談の際にアラスカのソ連兵パイロットの墓に参拝し献花した。米露では互いの領土にパイロットの墓があり、米露でお互いしっかりと管理している。日露の場合、90年代以降若干改善はされているが十分な墓の整備ができておらず、また日本の首相も訪問したことはない。またそれ以外にも北方領土問題に関するロシア政府の暴走に対して、引き続き注視することが必要ではないか。」と質問され、近藤様は「プーチンはソ連兵パイロットの墓へ十字を切ったが、これはソ連ではありえないことであり、文化を知ったうえで参拝するべきである。日本政府はシベリア抑留の被害者が全員いなくなる時期を待っているように感じており、私は風化させることがないよう引き続き活動していきたい。」と答えられました。

大学教授・国際音楽メンタルセラピスト協会会長 山西敏博様
大学教授・国際音楽メンタルセラピスト協会会長の山西敏博様は、「私の本業は言語社会学である。抑留者のお話に関連し、7月の埼玉新聞に、『モンゴル抑留者の望郷』という記事があった。田中利幸さんという声楽家が、モンゴルでの抑留時に日本に帰るという思いから歌を作り、歌っていた。それを譜面に残し、後世に伝える活動が掲載されているが、今度9月6日に田中氏とジョイントコンサートを浦安で実施することとなったためご紹介する。本題に入り、ヨーロッパ諸国の現状についてご報告したい。2024年8月にスロバキアでの国際学会に出席・発表を行った際に、隣国であるウクライナへの入国について、言語社会学という関係での現地視察として査証許可を取ることができた。中心地のキーウ周辺は戦禍がひどく立ち入れないため、スロバキア近くのウクライナ西部、ウジホロドという町を視察した。EU圏ではあるが国境で入国審査を受け町に入ると、ウジホロドは戦火の跡は見られず、平穏な日常生活といった風景だった。軍人の方がいたため話をし、彼らの国を守る思いや覚悟を知ることもできた。スロバキアでは盗難に遭ったが、警察の方と温かい交流をし、私がいつも感じている『苦難は幸福の入り口である』ということを改めて実感した。ドイツではきれいな街の中なのに、少し道を外れたトンネルの中には家を失ったアジア系の人々が路頭に迷っている、光と影を知ることができた。日本でも先日、佐賀県で技能実習生が強盗殺人をしたニュースがあったが、そうしたことを想起させる風景だった。次に国内の話として、能登半島地震における支援について、震災後に童謡メンタルセラピー支援として継続的に避難所等を回っており、今年の6月末に再度訪問した。輪島の町は瓦礫が解体されてはいたが、まだまだ復興道半ばといったところであった。最後に、アパグループの災害支援について。西日本豪雨への寄付や新型コロナへの宿泊療養施設、能登半島地震への支援物資提供など多岐にわたり支援されている。こうした活動に対し、『泊まって、食べて、訪れて、買って』応援したいと考えている。「贈る言葉」の歌詞にもある通り、『人は悲しみが多いほど、人には優しくできるのだから』ということを常に心に抱き、日本や世界で苦しんでいる方々への支援活動が皆さま一人ひとりからできるということを忘れないでいただきたい。」とお話しされました。

前横芝敬愛高等学校校長、学校法人鎌形学園、東京学館高等学校顧問 白鳥秀幸様
前横芝敬愛高等学校校長、学校法人鎌形学園、東京学館高等学校顧問の白鳥秀幸様は、「学び直しをテーマにした学校再生についてお話しする。私は20年前に千葉県の姉崎高校で校長を務めたが、着任前の数年間で生徒がバイク事故で数人亡くなっており、喫煙や窃盗が横行し荒れていて、退学者が100人もいるような高校であった。地域から廃校の声が上がるほどであった。元出光興産千葉製油所副所長の山田治男氏の力も借り、立て直しに尽力した。具体的には、650ページにも及ぶ5教科5科目の教科書を1から作った。学び直しをテーマに、基本的な足し算掛け算から始めた。私の実話をもとに、荒廃した高校の再生を描く『あねさきの風』というタイトルの書籍化を行い、昨年舞台化もしていただいた。ペンは剣よりも強しで、私の取り組みを多くの方々に知っていただけて嬉しく思う。日経新聞や産経新聞でも取り上げていただいた。産経新聞論説副委員長の沢辺隆雄氏や、藤岡信勝氏にもお越しいただき、実際に授業も受けていただいた。その後横芝敬愛高等学校の校長を6年務めた。当校のある銚子市は少子化が深刻で、近年の出生数は100人前後である。日本の学校のうち、3分の1ほどはこれらのような学び直しが必要な学校があるのではないかと肌感覚で感じている。こうした学校にもしっかりと手当をしなければ、日本社会は先細りになってしまうのではと危機感を抱いている。また反対に木更津高校という進学校では、私が勤務した当初は国歌斉唱や国旗掲揚をやっていなかったという事実もある。私の孫も重いタブレット端末を毎日持って行っているが、十分に活用できていない。授業を見たところ、書き順もいい加減でノートもチェックしていない。教育の現場では3つのミスである『見落とす、見逃す、見過ごす』を根絶することをモットーに、戦う校長として向き合ってきた。いま一度学び直しを徹底し、基礎を固めることが重要である。」と、教育における学び直しの重要性についてお話しされました。

一般社団法人空の神兵慰霊顕彰碑護持会代表理事 奥本康大様
一般社団法人空の神兵慰霊顕彰碑護持会代表理事の奥本康大様は、「私は市原市姉崎に住んでいる。数十年前、地域では、『姉崎高校にだけは行かないように』という話も出るくらい荒れていた。私も保護司や家庭裁判所の調停委員としての活動を通じ、彼らと向き合うことが大切だと感じている。なぜその人たちがそのようになったのかを真摯に考え向き合い、戦うことが大事である。勝兵塾ご参加の皆さまにも教育という国家の根幹に向き合っていただければと思う。」とお話しされました。
