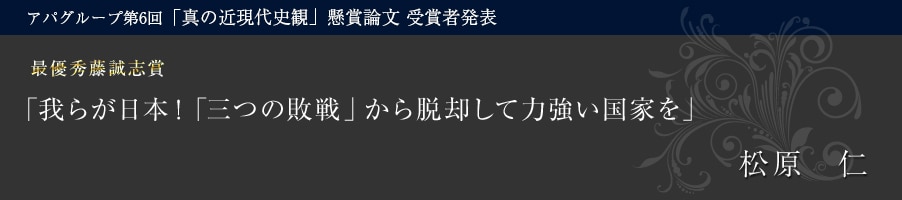第二次世界大戦に敗れてから、わが国では8月になるとこれを振り返る議論が盛んに行われる。戦争から60年余り経った今年も、様々な立場からこの問題について熱心な議論が交わされており、先の大戦に始まる多くの事柄が未だ過去のものではなく、正に現在における諸々の事柄を形作る基点であることを改めて思い出させてくれる。
この論文では、これまで様々な方々から伺った御見解や自らの検討を踏まえた上で、先の大戦の敗北の意義、敗北の結果生じた影響、及びかかる影響に対する対処を論じる。
本論は、いまだ検討の途上にある試論である。各方面からの御意見御批判を頂き、先の大戦の議論を深める一助となれば幸いである。
わが国の敗戦は3つに分けて考えることができる。「第一の敗戦」は、アメリカとの戦争に敗れたことにある。「第二の敗戦」は、第一の敗戦を機に国内において自虐史観が生まれ、これが根付いていったことにある。そして「第三の敗戦」は、戦争中に始まり今日に至るまで長い間続けられている情報戦における敗北である。
第一の敗戦は、如何なる国でも戦いに敗れれば味わう試練である。詩人杜甫の五言律詩に「國破山河在」(国破れて山河あり)という言葉があるが、如何なる国においても戦争における国土や都市の破壊は大きな虚脱感と敗北感をもたらす。しかし、多くの場合それぞれの国民や民族はそうした虚脱感や敗北感を乗り越えてきた。先の大戦において、首都東京は灰燼に帰し、広島と長崎は原子爆弾によって破壊された。これらの都市のみならず、多くの日本の都市は度重なる爆撃により廃墟と化した。多くの人たちが家を失い、日々の生活を営むための工場も破壊された。橋の下に多くの戦災孤児が集い、苦しい生活を送る光景もこの頃は普通に見られた。
こういった経験は、わが国だけのものではない。先の大戦の同盟国であったドイツは、日本以上に厳しい国家破壊の状況に遭遇した。日本においても、本土に対する戦略爆撃等により、多くの一般市民が命を失った。これに対しドイツでは、日本に対するよりも遥かに激しい戦略爆撃(投下された爆弾の量は日本の9倍)に加えて、その国土全体が戦場となったのである。国全体の状況を見れば、徹底した戦闘が行われたドイツの国土全体の崩壊は、日本の国土崩壊よりも決定的であった。また、戦中戦後にドイツ国内東部において行われたソビエト赤軍による略奪や強姦といった占領軍による蛮行も、日本本土においてはほとんど行われなかった。
しかし、ドイツも日本もこうした戦争による破壊から国土を再興することに成功した。つまり、戦争による国家や国土の破綻から、新たな国の都市づくり、インフラ整備に成功したのである。しかも両国とも著しい経済成長に成功し、奇蹟の復興と世界から称賛された。わが国に関しては、1960年代を中心とする高度成長期を通じてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国に発展することにより、1つ目の敗北は克服された。
では、第二の敗北についてはどうだろうか。私には、この第2の敗北は、ドイツよりも日本において顕著であるように思われる。なぜならば、日本は自虐史観により、その後の政策形成が大きく影響されてきたという意味において、世界でも稀と思われるからである。
私が五年程前の訪独の際会ったドイツ政府高官の発言は、今後ドイツは欧州連合(EU)の中心として活動していくという自信に満ち溢れていた。その発言には、自虐的な考え方は全く感じられなかった。その理由は、今日のドイツにおける建前は、ユダヤ人やロマ人の虐殺などを行ったナチス政府は、ドイツとは別のきわめて異常な人間の集団である、と言う立場にある。すなわち、先の大戦におけるドイツのユダヤ人虐殺を含む様々な残虐行為は、ナチスと言う犯罪集団によって行われた行為であって、現在のドイツやドイツ人は直接の加害者ではないと整理されている。むしろ、ドイツ国民そのものもナチスの被害者である、という認識である。残虐な民族浄化活動をしたドイツに、日本が持つような自虐史観が存在しないことは注目に値する。
決定的に国土が崩壊したドイツには無いのに、日本にのみ存在する今日の自虐史観は、敗戦自体により生じたものではなく、敗戦とは別のところで形成されたと考えられる。
極東国際軍事裁判(東京裁判)の判決理由の中に、明治以来のわが国の国策を一貫して否定する考え方が示され、自虐史観のよりどころとして一部マスコミを中心として宣伝されてきたことは否定出来ない事実である。東京裁判については、裁判が行われている当時から、その正当性についてインドのラダ・ビノード・パール判事により異議が唱えられた。戦後に新たに作られた「平和に対する罪」「人道に対する罪」などにより裁かれることは、裁判の基本である罪刑法定主義に反することは明らかである。また、「人道に対する罪」ということを考えるならば、広島や長崎に投下された化学兵器であり大量破壊兵器である原子爆弾の使用は「人道に対する罪」でなかったのか。また、一般の市民を事実上標的とした多くの都市における爆撃は「人道に対する罪」でなかったのか、など多くの点において、東京裁判に関しては、公平性に対する疑問がある。法学博士鹿島守之助氏は、戦後 『世界大戦の原因の研究』と言う書物の第四版への序文の中で、極めて鋭く東京裁判の違法性を指摘した。彼は「近い将来、政治もしくは法律を司る人間が問題提起をし、東京裁判の自虐的背景を乗り越えてほしい」と訴えている。しかし、それから半世紀以上を経ても事態は変わっていない。
いずれにしても、東京裁判の結果として、本来国家の生存に必要で、国際的にも広く認められた明治以来のわが国の様々な国策自体が、奇妙な形で否定されるに至った。
現在の日本国憲法が、GHQによりその草案が英語で作成され、その土台に沿って作り上げられてきたことは、今や広く知られた事実となっている。その後の調査や文献を見ると、当時のGHQ関係者が、自主的な民主的憲法制定に向けた動きの鈍い日本政府の対応に業を煮やし、頻繁に改正されるフィリピン憲法やアメリカ合衆国憲法を念頭に置いて、占領期間中の暫定的なものとして日本国憲法の原案を一気呵成に作成した様子が窺える。この国の最高法規である日本国憲法が、手続き上は法律に則って成立をしたものとはいえ、実態が日本国民の総意とは別のところで形成されたことは、同じ敗戦国のドイツとは大きく異なる。この点、ドイツは四つの占領国の意見の相違があったとはいえ、憲法に関しては占領軍に指一本触れさせなかった。
90年代初頭になると、こうした自虐史観は政界、官界、財界といった国家の中枢に蔓延するに至り、日本国民に自虐的な考え方を強要する様々な政策が日本国政府によって行われた。例えば、宮澤内閣時代に作られた教科書における近隣諸国条項がその一つである。私は、青少年の教育の原点である歴史教育の中において中国、北朝鮮、韓国などの近隣諸国の意向を忖度する必要を宮澤談話を通じて安易に決めてしまったことは、極めて遺憾な事だと思っている。いやしくも主権を持つ国家において、教育の権限は最も中核にかかわる権限である。その権限について他国から様々な注文を受けることを正当化すること自体が自虐的であり、主権侵害とさえ言えよう。
また、1993年に慰安婦問題に対応するために発表した内閣官房長官談話、いわゆる河野談話においては、「慰安婦問題に関して朝鮮における当局の強制連行を証明する資料がなかったが、資料がなかったからといって存在しなかったとは断言できない」という理由で、強制連行があたかも存在したかのような印象を与える言葉が海外に発信された。これも、日本政府により行われた自虐的な行動の典型的な例である。
尖閣諸島に日本政府がヘリポートを作ったのは1979年5月であり、30年以上も前のことである。しかし、その後日本政府は、中国を刺激するという理由から、ヘリポート設置後30年間、その補修を行わなかった。これは、国家として自らの行為を自ら縛る自虐的な行動である。今日同じように、尖閣諸島におけるヘリポートの建設を日本が行なおうとするならば、中国は大きく反発するであろう。
国会議員の靖国参拝も同様である。私はかつてベトナムを訪問した時に、ある女性教授と話をした。「靖国神社に参拝することに対して中国政府は非難をしてくるのですがどのように思いますか」という私の質問に対する彼女の答えは明快であった。彼女は「私たちの国でも日本でも、仏教の国では死んだ人は皆仏様です。生前の様々な行動や悪行は水に流れるのです。靖国神社に参拝するのは一人の人間として当たり前だと思います」と答えたのである。
それでは、こうした自虐史観の原点である東京裁判史観の克服に向けてどのような対応が必要だろうか。
今日の日本と国際社会の平和的な枠組みを形成する大きな要素が、サンフランシスコ平和条約である。その第11条では、東京裁判の判決を受諾することを前提としている。その枠組みの尊重は、今日の国際社会の平和的な枠組みの一部を形成するものである。したがって、判決自体を覆すのは難しいとしても、判決の主文ではなく、判決を導き出した判決理由を変更することを含め、今後専門家の間での議論の進展が求められる。
こうした自虐史観からの脱出は、その必要性が時間の経過とともに減じるものでは無い。物理的な傷は癒えることはあるとしても、精神的な自虐史観のような傷は癒えることはない。この克服に向けて、我々は戦わなければならない。
ここで私は、日本はさらに第三の情報戦における敗北を喫していることを指摘したい。
情報戦における敗北により、国際社会において日本が極めて悪い国であるという印象を世界に与え、そして日本に対しては日本国民は常に自虐的に振る舞わなければいけないという精神構造を押し付けるものとなった。わが国の第三の敗戦は、戦争中から用意周到に仕組まれ、そして今日になってももまだ現在進行形で続いている。例えば、南京事件(いわゆる南京大虐殺)、日本海呼称問題、慰安婦問題といった事案を例として挙げることが出来る。
南京事件については、30万人の殺害など、当時起こった国際法規違反の行為をはるかに超えた、あり得ない形の残虐行為が捏造された写真等を用いて喧伝されている。また、韓国内のみで用いられるに過ぎない「東海」という語があたかも日本海を指す国際的に正当な呼称として、国連などの場で広く提案されるに至っている。慰安婦問題については、存在しない朝鮮人女性に対する軍の強制連行などが韓国により宣伝されている。
ここで問題となるのは、国際社会が何を事実として認識しているかである。
先日ある国の外交官と会食をした。話が南京事件や慰安婦問題に移ったときに、その外交官は「恐らくそうした事実はなかったと認識している」と語った。彼が更に語った以下のことは、非常に示唆に富んでいる。
現実がどうであるかが問われるのでなく、どのような現実が伝えられるかが問題である。事実に対しては、様々な見方がある。とりわけ国際社会における事実の認定は、双方で合致しないのは常識である。そこでどのような事実を認定させるかということで、情報の戦いが始まる。日本人は、黙っていても事実は事実として認識されると思っているかもしれないが、国際社会はそれほどナイーブ(単純)なものではない。事実が事実と認識されるためには、多くの汗をかかなければいけない。その努力を怠っていれば、当然事実ではないことが国際社会に認定される。
私は、この話を聞いて2003年のイラク戦争を想起した。イラク戦争前夜、アメリカやイギリスは、イラクの大量破壊兵器保有を疑い、イラク攻撃が必要と考え、イラクを攻撃した。結果的にはイラクの大量破壊兵器保有は証明されず、イラク攻撃の理由は事実に反することが明らかになった。しかし、その時は「イラクは大量破壊兵器の有無を査察されるべきということを定めた国連安保理決議1441を妨害し、違反している」と言うことを踏まえて、アメリカやイギリスによるイラク攻撃は行われたのである。これは、何が事実であったかということよりも、国際社会で認定された事実によって、歴史が動いた一例である。
そしてこうした事実の認定にお墨付きを与えるのは、国際連合であったり、アメリカの議会であったりする。アメリカ議会における慰安婦非難決議の採択は、それが事実であったと国際社会に認定される第一歩となる。
慰安婦決議と類似したものに100年前のアルメニア人虐殺事件に関するトルコへの非難決議がある。アメリカ議会におけるアルメニア系議員によって提起されたトルコ非難決議は、トルコの政府とマスコミと国民との徹底した闘争により反故にされた。この時、トルコのマスコミと政府は、この決議の採択がアメリカ軍に対するトルコ国内の軍事基地の使用拒否に繋がることを示唆するなどして強烈なロビー活動を展開し、アルメニア系議員による決議採択への動きに対抗した。
類似の事例であるにもかかわらず、日本政府は米国内の韓国系住民の強い支持を受ける議員によって提起される慰安婦非難決議に対して対抗したことはない。正にこうしたことが日本の情報戦における敗北を決定的にしている。
前述の外交官は、更に注意深く以下を指摘した。
30年以上かけて南京事件や慰安婦問題は国際社会に事実として受け入れられてきた。こうした状況を変えるには、同じように何十年もの時間が必要である。短期間で世界に受け入れられた認識を覆すことはできない。そのためには、マスコミや世論を形成するPR会社を通じて様々な工作を行う必要があり、莫大な手間暇と費用等が必要である。今日の状況は日本の政府とマスメディアが情報戦にしっかり取り組まなかったことに原因があり、むしろそのことを日本は反省し、今後の糧とすべきである。また、例えば慰安婦像が様々な場所に設置されることに対して即時撤去を主張することはかえって相手の土俵と戦略に乗ることになり情報戦においては通常行わない。むしろ、そこに目を行かせないようにして時間をかけた様々な工作によってこうした事実がなかったことを浸透させることが重要である。
例えば、第二次世界大戦の時に多くのビザを発給し6000人以上の多くのユダヤ人の命を救った、イスラエルにおいては尊敬をされ続けている杉原千畝のような、ヒューマニズムを実践した人の像を慰安婦像の横に立てることなどを実践してみてはどうか。そのことによって、戦前の日本人の中には人間尊重の観点から危険を冒して行動した人物がいることを、世界中に知らしめることの方が有効だと考える。
こうした行動が行われれば、世界に大きな影響力を持つユダヤ系のマスコミやユダヤ系人脈が日本人を悪しき存在とするプロバガンダに対して、国際的な認識をプラスに改める有効な材料を提供するであろう。
なお、南京事件については、20年程前に当時の江沢民総書記を中心とする首脳部の意向を受けた自民族中心主義に基づく国粋主義教育により中国国内に広く浸透した。この国粋主義教育の結果、終戦直後の中国の国民より、今日の中国の新しい国民の方がより強い反日感情を持っているという。つまり情報戦は今日も現在進行形で続いており、永続的に行われるということである。
日本人が自信を持つ国民となるためには、本論で議論してきた「三つの敗戦」を乗り越えることが必要である。わが国が経済的に大きく成長して「第一の敗戦」を克服した今日、「第二の敗戦」と「第三の現在進行形の敗戦」を乗り越えることが急務となっている。
財団法人日本青少年研究所が実施したアンケートによれば、自分は駄目な人間だ・自信が無い、と考える中学生は、日本で56%、アメリカで14%、中国で15%であるという。そして、日本の高校生の66%、アメリカの高校生の22%、中国の高校生の13%が自分に自信がないと回答している。
自信は、それぞれの人間が何かを行うにあたり最も重要な力となる。自信のあるところに活力と成功はもたらされる。今後の日本が世界の中で、名誉ある立場を持ち、活動を続けるには、青少年の自信を取り戻すことが重要である。しかし、自信は、自虐的な環境や教育の中で取り戻すことは困難である。かつてプラトンは「国家は大文字の個人だ」と言ったが、自信ある個人が集まれば自信ある国家が生まれ、自信ある国家が生まれればそこに自信ある個人が育つのである。
とりわけ第三の敗戦、つまり「情報戦の敗北」は、戦後半世紀以上経って、今や日に日に危機的な状況になっている。敗北はより深刻になっているのである。私が本論で読者に訴えたいことは、まずは自虐史観と戦い、これを克服することを通じ、わが国のよって立つところを確立すること、加えて、未来の子孫のために、長期的な戦略を立てて情報戦の敗北を乗り越えることである。この2つが21世紀にわが国が諸外国との間で真に平和的で友好的な関係を確立し、国際社会で名誉ある地位を占めるために必須であるということである。
具体的な戦略の一つとして、日本による多額の分担金拠出にもかかわらず、国際連合において未だ存在する敵国条項を、ドイツと共同して撤廃する取り組みを加速することは検討に値する。このような取組みを通じて、我々がこれまで平和を愛する諸国民と共に築き上げてきた、正義と秩序とを基調とする国際平和を、一層確かなものとしていくことが何よりも重要である。
私は、心ある読者とともに、この三つの敗戦からの脱却という大きな戦いに向けて全力を賭けて取り組むことを、今ここに誓いたい。