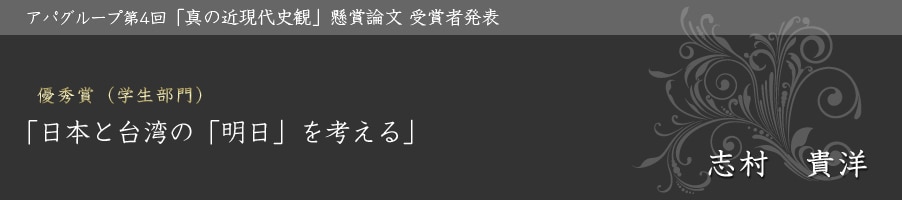二〇一一年は中華民国建国百年という節目の年である。しかし中華民国と聞いて、はたしてどれほどの日本人が台湾を想起できるだろうか。
日本と台湾の繋がりは、他の国々よりも緊密な関係といっても過言ではないだろう。東日本大震災の直後、台湾ではチャリティ番組などを通じて百億円以上の義援金が集まり、三月十四日には救援隊が日本に到着した。
ただし台湾の隊員派遣は震災直後から表明されており、受け入れまでの「空白の時間」が不可解にも生じた。すでにお気づきかもしれないが、台湾の隊員派遣が遅れたのは中国への配慮があったからである。十三日に中国の救援隊が現地入りするまで、台湾の受け入れが表明されることはなかった。
一九七二年の日中国交正常化にともない、日本は台湾と断交した。第二次世界大戦以前から中国大陸では国民党と共産党による内戦が勃発し、大陸のあちこちで一進一退の攻防を繰り広げた。一九三七年の支那事変で両者は和解し、日本に対抗する動きをみせたが、戦後構想の不一致で一九四六年から内戦が再び勃発した。
戦後日本が国交を断絶した国家は、最たる親日国家の台湾、ただ一国のみである。国交を結んだものの、領土や歴史問題で傲然たる態度をとる反日国家、中国。一方で、四十年前から国交がなくとも交流が盛んで、隣国の非常時にいち早く手を差し伸べた台湾。
不確かな状態が続くなか、日本と台湾はどのようにして一定の関係を維持し続けたのか。
今回は闇に葬られた日台の歴史について触れるとともに、台湾でお会いした誇り高き台湾人たちの言動を踏まえ、これからの日台関係について考えてみたい。
一九四九年六月、ある日本人が通訳たちを引き連れ、沈没寸前の漁船で宮崎から台湾に向かった。その日本人の名は根本博である。根本は陸軍大学校を卒業後、陸軍中将、北支那方面軍司令官にまで上りつめたエリート軍人だ。復員後は隠遁生活を過ごしていたにもかかわらず、根本は「ある決意」を胸に、途中で船が座礁しながらも台湾に渡った。
台湾へ渡る以前、根本中将は中国大陸で「内蒙古の戦い」の指揮にあたった。この戦いは昭和二十年八月二十日、つまり戦後にソ連軍と繰り広げられた戦いである。戦後ソ連軍は千島列島の北東に位置する占守島を侵攻したが、中国大陸でもソ連軍と一線を交わしていたことはあまり知られていない。当時駐蒙軍を統率していた根本中将は在留邦人の祖国帰還に力を注いだ。無事に在留邦人を本国へ帰還させるにはソ連軍と戦わねばならないが、本国からの武装解除命令に背くことは戦争犯罪を意味していた。窮地に追い込まれた根本中将は、軍命に従わず戦うことを決意した。中将の壮絶たる覚悟に部下たちも共鳴し、駐蒙軍は中国の張家口でソ連軍と激突した。この戦いで駐蒙軍はソ連軍を退け、四万もの在留邦人が日本へ脱出する突破口を開いたのだ。
四万人の邦人脱出を成功させた後、根本中将は中華民国元首・蒋介石と会談している。根本は敗軍の将として死を覚悟していたが、蒋は根本の罪を問おうとしなかった。蒋は一九四三年のカイロ会談で、天皇制のあり方を日本国民に委ねるよう発言したが、おそらく日本やアメリカの支援を受けて共産軍に対抗する狙いがあっただろう。だがそれでも根本は、国体を守ってくれた蒋の言動にいたく恩義を感じていた。
蒋を助けるため、根本は命懸けで台湾に渡った。しかし国府軍の壊滅をせんがため、共産軍は最後の一撃を企てていた。危機的状況に追い込まれた国府軍に、根本はこれまで陸軍で培ってきた経験と戦術を惜しみなく提供した。総司令を任されていた湯恩伯将軍は、日本人である根本のアドバイスを誰よりも尊重した。その結果、台湾の命運が懸けられた金門島での戦いで、国府軍は圧倒的な軍事力を有する共産軍を退けた。この戦いの勝利によって、根本は蒋介石に対する恩義に報いたのであった。
日本とって台湾とは、歴史を共有できる数少ない国の一つである。根本中将の行動があってこそ、日台の歴史は私たちの世代に継承されたのではないか。根本中将の一生に触れたとき、ふと思った。
いっぽうで、蒋介石の歴史的評価がいまなお賛否両論であることも忘れてはならない。二・二八事件に代表されるように、蒋介石が本省人に対して行った弾圧は消し去ることのできない事実である。しかし同時に、一人の日本人が蒋介石のため、ひいては台湾のために戦ったという事実も語り継ぐべきだと私は考えている。
根本博の生きざまに感銘を受けた私は、フジサンケイビジネスアイと台湾の行政院が主催する「日台文化交流 青少年スカラシップ」に論文を応募し、三月下旬に台湾を訪れることができた。今回の台湾研修でお会いした人々は、日本による台湾統治をあらゆる視点から評価しており、どれも心に残る話ばかりであった。
私たちは戦争を知らない世代である。学校では戦争について語られることもなかったし、教えられてきたのは嘘で塗り固められた日本軍の蛮行のみである。戦時中の状況を知るうえで、やはり当時を生き抜いた人々の証言は貴重だ。私も祖父母に戦争中の思い出を尋ね、とくに戦後復興の苦難を聞いたときは胸に突き刺さる思いだった。しかし私の家族で出征した者はおらず、今回初めて日本統治下を生き抜いた台湾人とお会いすることができた。
司馬遼太郎著『台湾紀行』に登場する「老台北」こと蔡焜燦氏は、日本の統治政策を後世に伝えようと奮起する数少ない一人だ。
顎鬚を蓄えた蔡氏が「お土産」といって渡してくれたもの、それは四百ページにも及ぶ『綜合教育讀本』の復刻版であった。蔡氏の母校である台中の清水公学校では、当時の学校教育では珍しく有線放送を利用した授業がおこなわれていた。金色に輝く読本は、授業で放送されるレコードの内容を活字にしたものであり、蔡氏は来る日も来る日も読本にかじりついていたという。日本の学校でさえ校内有線放送の設備がなかったにもかかわらず、清水公学校には完備されていた。しかし終戦とともに国民党政府によって放送設備は破壊された。
一時は読本の復刻を諦めたという。しかし日本の統治政策を固く信じる蔡氏の熱意が周囲に伝わり、『綜合教育讀本』の復刻までにいたったのであった。
日本統治下に生まれ、日本語教育を受けてきた方々が集う会、「友愛会」の会員からも話を聞くことができた。
一九九二年、台北で特許事務所を経営していた陳燦暉氏が仲間とともに「友愛日本語クラブ」を結成し、現在では友愛会へと発展した。
なぜ陳氏は友愛日本語クラブを結成したのだろうか。
台湾の歴史教育が蒋介石の下「大中華思想」で反日的だった時代、日本語が堪能な陳氏は文化交流の催しで通訳のボランティアを進んで申し出ていた。陳氏はあるとき、日本語を学ぶのが困難で起こった失敗談を耳にした。ある台湾人通訳が「あなた様」と訳すべきところを「貴様」と言ってしまい、日本人を激怒させたというのだ。
この話を聞いた陳氏は「美しく正しい日本語を台湾に残す」ことを胸に秘めたのであった。しかし当時は戒厳令下にあったため、日本語の勉強会を大々的に開催することは困難であったという。
会の冒頭で張文芳代表から月例会の資料が手渡された。資料には友愛会の方々が書かれた文章が掲載されているが、その文章はまったく遜色がなく見事な文体であることに驚かされた。いくら戦時中に日本語教育を受けたとはいえ、その読み書き能力を維持するには常日頃の努力が欠かせない。しかも今日では日本語を学ぶ必要がないのだから、その姿勢には頭が下がる。
同じ日本語教育を受けてきた世代でも、韓国人は日本人と会っても日本語を話そうとはしないらしい。今でもそうだが、日本統治の象徴である日本語は、韓国人による日本叩きの対象である。そのため日本語を公の場で話すことはご法度なのだ。
いっぽうで同じ統治下であった台湾の場合、韓国とは対照的だ。日本語が話せる台湾人は積極的に話しかけるのだ。私も現地で体験したが、街で日本語を話していると年輩の方に声をかけられた。行天宮でもご婦人から話しかけられ、横浜の山下公園や中華街の話でずいぶんと盛り上がった。そしてなによりも忘れられないのは、どの会話の最後でも東日本大震災を心配し、「頑張れ」と励ましの言葉をいただいたことだ。多額の義援金からも日本への高い関心が感じられたが、それを改めて台湾で認識することとなった。
日本の統治政策によって台湾近代化の礎が築かれた、これが蔡氏の評価である。しかし、ある会員の経験談を聞き、日本の統治政策が全ての台湾人に受け入れられなかったことを痛感した。
日本の統治下では内地人の優遇措置がとられたため、台湾人は進学や就職において不利な状況におかれていた。友愛会の会員にもそれを肌で感じており、ある人は自分よりも成績が悪い日本人が優秀な学校に入学できたことを悔しがっていた。競争率の高い学校には内地人枠が確保されており、必然的に進学は日本人のほうが有利である。
彼らのように台湾人が自らの艱難辛苦を私たちに伝えるのは、かつての祖国・日本に対する一種の「愛情」ではないだろうか。
台湾の場合は前述の通り、経験に基づかれた事実をありのままに語り、その叱咤は日本への激励に繋がるものだ。しかし南京大虐殺や、いわゆる従軍慰安婦といった根も葉もない「事実」を「叱咤」する中国・韓国は、決して日本を「激励」するわけではない。すべては自国の利益のためだけである。彼らには「中華思想・小中華思想」の考えが根幹にあり、日本を貶めることを厭わない歴史的事実が存在する。
日本語を学び、後世に歴史を継承する台湾人の思いはなかなか伝わってこない。たとえば、日本人技師・八田與一によって設計された烏山頭ダムを世界文化遺産に登録しようと、台湾で署名活動が行われている。台湾は世界文化遺産に関する条約に批准していないため、日本の協力なしに登録申請は不可能なのだ。しかしこの活動を報道した国内メディアはごく一部である。日本の名誉であるにもかかわらず、他国のアイドルばかりを特集する既存のメディアはもはや存在意義を失っている。私たち一人ひとりがアンテナを張り、彼らの声に耳を傾け、それを発信していく力が今後必要になるだろう。
三月二十三日、台北の淡水で李登輝元総統を表敬訪問した。台湾の民主化を成し遂げた人物がご多忙のなか、私たちと会っていただけるということで感無量であった。
李登輝氏は予定よりも一時間多い、二時間半もの時間を割いて熱弁をふるった。会談では武者小路実篤の文章「君は君、我は我、されど仲良き」を引用し、中国とは「けじめをつけた」関係を保つこと、日本とはさらに緊密した関係を築くことを強く訴えた。
事前の説明で、李登輝氏との会談中に学生からの質問を受け付けることを聞いていた。そこで私は二つの質問を用意した。
まず一つ目は、「誠實自然」という言葉に込められた思いである。
靖国神社では七月の中旬に「みたままつり」が開催され、各界の著名人によって揮毫された雪洞が神門から中央鳥居にかけて並ぶ。昨年のみたままつりでは、なんと李氏が雪洞を揮毫されていたのだ。そこには「誠實自然」という四文字が記されていたが、私にはこの言葉の意味を推し量ることができなかった。
この質問に対して李登輝氏は、「誠實自然」という言葉は日本文化の象徴であると答えた。まず「誠實」についてだが、これは日本人の精神面を表しているという。日本人が誠実であり続けられるのは伝統を重んじてきたからであり、その伝統とは武士道に通ずるものだと述べた。李氏は二十二歳まで日本人として育ち、鈴木大拙や西田幾多郎の本に出会い、自己修練のために座禅に励んでいた。日本で受けた教養・教育が精神的成長をもたらし、総統としてリーダーシップを発揮できたというのだから説得力がある。
「自然」について、李氏は茶道や華道など「道」といわれる文化の発展を例に挙げた。これらは「自己意識の深化」がねらいであり、時間と空間を通して意識を深めることに日本人は取り組んだと説明した。このような自然との調和を志す日本人の生活が、李氏にとって日本人の象徴であるのだ。
さてもう一つの質問は、「日台の国交は再び結ばれるのか」である。 国交が断絶されたとはいえ、経済・貿易・文化・スポーツなどの各種関係は「実務的に」維持されている。一方で政治ルートがないために不都合が生じることは、当時の外交官からの証言から推察できる。世界の勢力均衡を考慮して、国交締結が容易ではないのは百も承知である。しかしそれでも、これからの日台関係を議論するなかで、総統まで上りつめた人が考える「国交の意義」を聞かずにはいられなかった。
この質問に対して、李氏は淡々と答えを述べた。
「現状では難しい。日中関係、さらには対中・対米関係を考慮すれば日台の国交が結ばれるには程遠い環境である。しかし国交が結ばれていなくても、日本人は台湾に来て台湾のことを知ることができる。」
当初の予想通り、きわめて「簡潔な」回答だった。だが李氏が最後に放った一言はとても印象的だ。
「日台の国交が樹立されるとならば・・・それは『何らかの事件後』、『台湾が自立したとき』だろう。」
李登輝氏の発言はどれも含蓄のあるものばかりで、二時間半という時間はあっという間に過ぎ去ってしまった。会談では台湾独立に対する静かな熱意、そして政治的な質問でも率直に答えてくださる李氏の寛大さをうかがい知ることができた。すべての言葉を咀嚼するには時間がかかりそうだが、必ずや日台両国の道標になるはずだ。
私は中学生のころから、新聞をそのまま捨てるのはもったいないという理由で新聞記事の切り抜きを始めた。ときどき思い返しては記事を読み返すのだが、二〇〇二年の記事に「乗るバス間違えた日本」という題名の記事を発見した。
二〇〇二年が日台断交三十年目にあたるということで、断交時、駐日大使館に参事官として勤務していた林金莖国策顧問(取材時)がインタビューに応じた。
林氏は「バスに乗り遅れるな」と日本が中国になびいたことで、田中角栄首相は「乗るべきでないバスに乗ってしまった」と当時を振り返った。また林氏は、三十年の間に日中関係は「一ミクロンも進んでいない」と厳しく評価している。
まもなく日台断交から四十年が経とうとしているが、林氏の言う通り、日本は乗るべきバスを間違えたのだろうか。もちろん国交正常化が果たされていなかった場合を考えても、それはあくまで仮定の話にしか過ぎない。しかし日中関係が「一ミクロン」でも進んだかといえば、答えは否である。尖閣諸島などの問題を鑑みれば、むしろ一センチ、いや一キロ以上遠ざかってしまったに違いない。
ひるがえって日台関係はどうだろうか。国交なき関係といえども貿易や人的交流は盛んに行われている。
貿易面では、台湾にとって日本は最大輸入相手国である。そして来月九月には「日台民間投資取り決め」が調印される予定で、特定措置の履行要求の禁止や内国民待遇が盛り込まれることから、投資促進、相互投資の活性化によって日台のより密接した関係を構築することが期待される。
人的交流において四十年前は年間四十万人ほどであった日台の往来が、二〇一〇年のデータでは二百三十万人あまりにまで膨れ上がった。二年前には日台ワーキングホリデー制度が実施され、台湾側からの申請者は制限枠の二千人を二年連続で超過するほどの人気ぶりである。
三月の訪台では私たちと同世代の台湾人とも話すことができた。大学で日本語を専攻する学生たちが話す日本語の流暢さには驚かされたが、日本語を履修している高校生もこれまた流暢な日本語を話すため二度驚かされた。
日本と台湾は、日本統治下の時代(厳密にいえば鄭成功の時代からかもしれない)からこれまで、互いに辛酸を嘗めてきた間柄である。国交が断絶されてもなお日台の関係が良好でいられるのは、歴史的事実を重んじた先人たちのたゆまぬ努力のおかげである。しかし日台関係の一時代を築いた人々のなかには鬼籍に入られる方も少なくない。先ほどの新聞記事でインタビューを受けた林金莖氏もその一人である。
彼らの努力がいま、私たちに受け継がれようとしている。
二〇一二年は日台断交から四十年目にあたる年である。来年を迎える前に日本人一人ひとりが台湾との「明日」を考えよう。決して早すぎることではないはずだ。